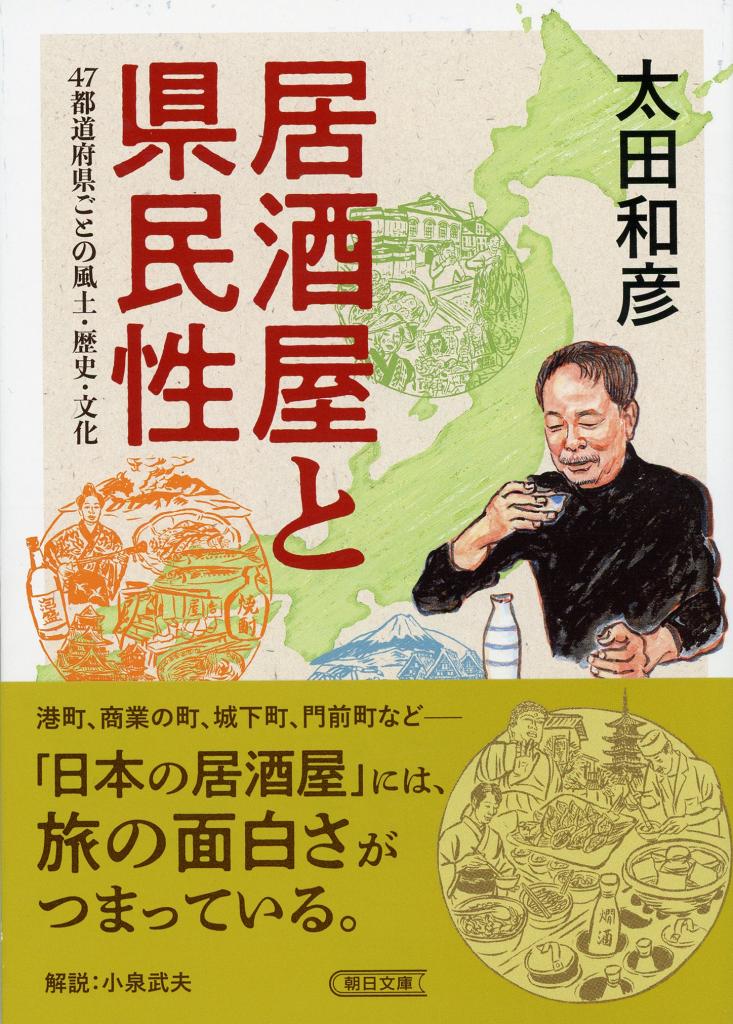
※本の詳細をAmazonで見る
また、知らぬ同士がすぐ「友達ばい」と意気投合するが、翌朝はけろりと忘れて「あんた誰や」になる。東北の人は無口でなかなか打ち解けないが、気を許すと律義に続くのとは大違いだ。東北人と福岡人が屋台に並ぶと見ものかも知れない。
祭好き、インパクトある食べもの、外で飲むのを好む、開放的な性格、などはラテン的気質の県民性といえるだろう。
北九州小倉は、炭鉱景気、八幡製鉄所の24時間稼働、その石炭輸送や玄界灘漁業の大型港として活気づき、川筋(かわすじ)気質といわれる男っぽい仁侠(にんきよう)の気風を作った。
小倉生まれで玄海育ち
口も荒いが気も荒い
村田英雄の熱唱に歌われる「無法松の一生」は小倉生まれの作家・岩下俊作の名作で、荒くれ男の中に気高い魂があるという主人公は日本で最も人気のある男像かもしれない。
市内、紫川支流の舟運荷揚場が魚市場に発展したのが「旦過(たんが)市場」だ。市場好きの私が選んだ日本5大市場は、釧路「和商市場」、秋田「市民市場」、金沢「近江町市場」、大阪「黒門市場」、小倉「旦過市場」。
いずれも市民生活に密着しているのが条件だが、旦過市場の幅せまくゆるやかに曲がる通路の両側は、食品、洋品、雑貨など個人商店ばかりが軒をつらね、朝から夕方までにぎわう。横に入ったY字の一角は一番古いままの木組み天井に裸蛍光灯が懐かしく、乾物「岡本商店」の、天狗印奈良漬、カモ井の佃煮など、10いくつも並べた古い木彫り看板がすばらしい。清酒看板をいくつも上げた酒屋「あかかべ」は立ち飲みが人気だ。小倉はこの「角(かく)打ち=冷や酒を枡の角から飲むのをこう言った」立ち飲みが盛んで、それは製鉄所全盛時代・昼夜3交代制の朝方終業者のためだった。「30分以内」の貼紙があるが、かつてはお釣りを渡す前にツイーと飲み終わっていたと言う。古い建物は戦後に役目を終えた小倉練兵場の軍馬舎の移築というのも興味深い。
日本でいちばん古いアーケード商店街「魚町銀天街」真ん中の、小倉名物の居酒屋「武蔵」は、角地に立つ大楼で玄関も2つあり、1階カウンターよりも2階の大広間からどんどん埋まってゆく。何十畳もの畳座敷に衝立(ついたて)で適当に仕切った座卓が10いくつも置かれ、中高年も、若いのも、男女カップルも、女子会も、広間で一堂に飲むのが小倉流。1人酒は似合わず「おーい、こっち来いや」とたちまち仲間だ。男たちの体を張った仕事はつべこべ言わず仲間とがんがん飲んでまた明日、の気風を生んだのだろう。小倉は「男は男らしく、女は女らしい」古きよき九州濃度がしっかり残っている町だ。



































