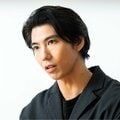「つらい」や「悲しい」といった感情表現が、共感を求めるだけの言葉として受け止められることもある。SNSでの「お気持ち」が、面倒なことになるなんて……。AERA 2019年12月16日号では、SNSでしばしば論争になる「お気持ち論法」を分析した。
【図】ユーザー離れが進んだのは… SNSの利用者数はこんなにも変わった!
* * *
返しても、返してもスマホの通知が鳴りやまない。武蔵大学社会学部の千田(せんだ)有紀教授のツイッターには、執拗なリプライが届いていた。
ことの発端は、千田教授が書いたウェブ上のニュース記事に、複数のユーザーから届いた反論だった。当初は論理的に話していた。だが、途中で千田教授が反論へのリプライに、「悲しい」「ショックだ」などと気持ちをのせた瞬間に火がついた。議論に私的な感情を交える「お気持ち論法」だと非難が殺到したのだ。
SNSで社会的な問題に個人の「快」や「不快」を交えて書き込むことを「お気持ち」だと揶揄する投稿が目立つようになった。たとえば、他人から指摘を受けるや否や「あなたがそう受け止めるとは思わなかった。残念です」「そう言われるとは思いませんでした。傷つきました」と返すと、すかさず「論理と感情は分けろ」といった指摘を受けるやり取りだ。
このようなネットの風潮について、ITジャーナリストの高橋暁子さんが指摘する。
「ツイッターが広く使われ始めた頃から、自分の気持ちが一番だという『お気持ちヤクザ』や、人の発言に傷つきやすい『繊細チンピラ』という呼び名が目立ち始めました」
気持ちを表明することで、自分を落ち着かせようとする。相手の情に訴えかける効果がある一方で、マイナスに受け止められてしまうこともある。それが噛み合わずに、しばしばネット上で“論争”になる。
自分の価値観に近い人をフォローできるツイッターでは、「自分の考えがすべてだ、と思い込みがち」と高橋さん。だが、なかにはフォロワーが多い人を引きずり落とそうと監視し、感情表現などを集中的に叩くアンチのような人もいるという。