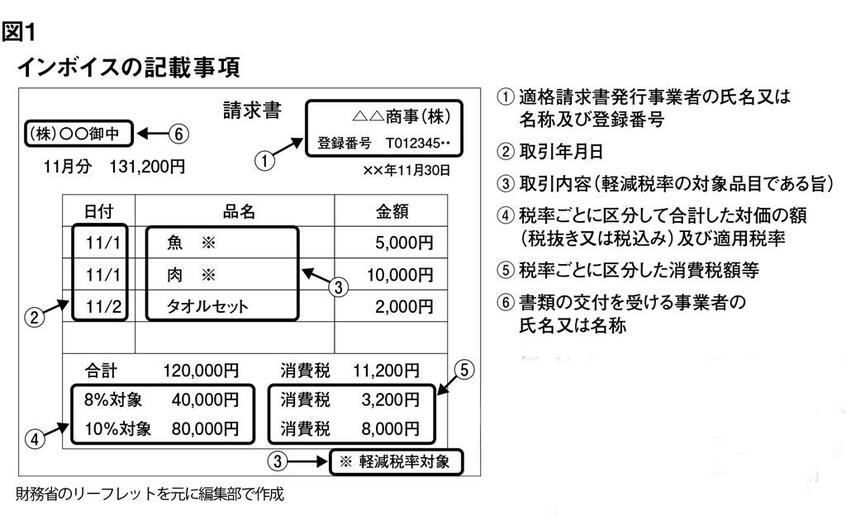
ただでさえ不安定なフリーランスが、コロナ禍や物価高のただ中で、払う必要のなかった税金をわざわざ志願して“納めさせていただく”? これほどの不条理があろうか。
非課税事業者のままでいる選択肢は取りにくい。アダム・ロドリゲスや、イ・ビョンホンの吹き替えで知られる阪口周平氏(45)が教えてくれた。
「ある声優が所属事務所のデスクに、インボイスの登録がないと仕事が減るかも、と言われたと聞きました。経理部門からの圧力で、自然とそういう流れになるのではないかという話だったとか」
“そういう流れ”とは何か。フリーを使う発注側は、徴税当局の回し者なのか?
事はそう単純ではない。1989年に導入された消費税は、過去三十有余年、政府やマスコミが喧伝し続けた「広く薄く中立的でシンプル」だという刷り込みとはまるで裏腹の税制だ。筆者は逆に、弱者のわずかな富をまとめて強者に移転する税制に他ならないと断じよう(全体像は拙著『決定版消費税のカラクリ』<ちくま文庫>など参照)。
消費税法によると、そもそも納税義務者は消費者ならぬ年商1千万円超の「課税事業者」。かつ、原則あらゆる商品やサービス(医療や居住のための家賃など社会政策上の例外あり)の、すべての流通段階で課税される。
■生き残りのため弱者にしわ寄せ
課税事業者が常に「コスト+利益+税」を積み上げた値決めをできるなら、まだしもだ。だが市場経済の日本で、そんな殿様商売が可能な事業がどれほど存在するか。取引先との力関係が弱ければ弱いほど、競争相手に負けない低価格設定をと利益を削り、コストダウンするしかない。などと言えばもっともらしいが、所詮(しょせん
)はより弱い立場の従業員や仕入れ先が、玉突きよろしく負担を押しつけられてきたのが実態だ。
いわゆる「転嫁」の問題だ。もちろん元請けが下請けに無体な値引きを迫れば独禁法の「優越的地位の濫用」に該当する。「転嫁対策特別措置法」が制定された近年は、公正取引委員会もそれなりの意欲を見せていなくもないものの、もはやズタボロ、“安いニッポン”とまで揶揄(やゆ)される経済社会で通用するはずもない。





































