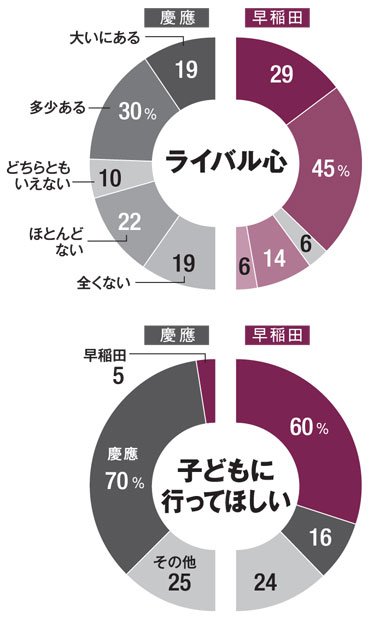
名門私大として、事あるごとに比較される早稲田と慶應。お互い母校のどこに誇りを持ち、相手校をどう捉えているのか。彼らの本音を探ってみた。
由緒ある文化施設、イギリスはロンドンのバービカンセンターのレストランに集まった同窓生は、200人近かった。
2011年秋、英国三田会の総会に参加した1999年法学部卒のAさん(40)は、その衝撃をこう振り返る。
「これほど人が集まるとは思っていませんでした」
当時、自身は仕事を1年間休み、エディンバラに留学中で、慶應出身の友人に誘われての参加。志木高から大学まで慶應で過ごし、同窓生と親しくしてきたが、三田会の結束力を目の当たりにしたのは初めてだった。
会話が弾むよう卒業年次順にテーブルはまとめられ、代表のあいさつや乾杯にはじまり、フルコース料理を堪能した。終盤には、東京─ロンドン間の往復航空券など豪華景品が当たるくじ引きも行われた。
「会の締めには、全員で肩を組んで『若き血』を歌いました。三田会のネットワークの強さを感じた瞬間でした」
慶應といえば、三田会。慶應の魅力に、卒業後の人脈を語る人は少なくない。
85年法学部卒で高校の教師をしているBさん(56)も、
「大学を離れてからも、困ったとき助けてくれたのは、塾員、塾生諸君でした」と振り返る。
大学院生時代は割のいい家庭教師や翻訳などのアルバイトをあっせんされ、社会に出てからは慶應出身の政経教師の勉強会に参加し刺激を受け、そのつながりは今も続くという。
早稲田にも稲門会という同窓生組織がある。
「稲門会は、三田会に負けていませんよ!」と息巻くのは、損害保険会社に勤める早大90年法学部卒のCさん(50)だ。
Cさんは在学中も卒業後も、母校に思い入れを感じたことはなかった。佐賀に単身赴任した40代になって、考えが変わった。稲門会に行ったのがきっかけだ。
「『ひとりで寂しいでしょう』と、家族のある同窓の部下に勧められて、食事会に参加するようになりました。佐賀といえば、創設者・大隈重信公の出身地。毎月命日に集まったり、稲門会員の文化人を招いたりと、非常に充実していました」
鳥栖市長夫妻から市政についての話を聞き、同窓生らと大隈公の墓に詣でた。もちろん、こちらも締めは歌だ。





































