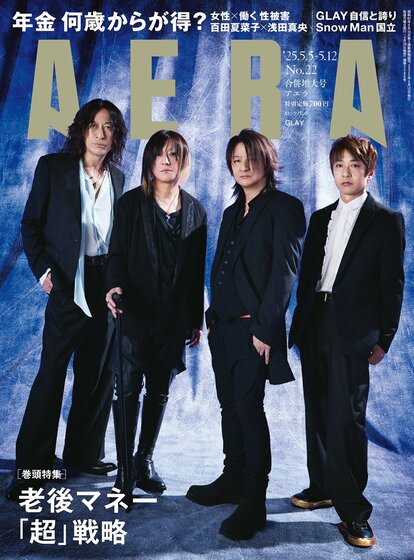放送作家・鈴木おさむ氏の『週刊朝日』新連載、『1970年代生まれの団ジュニたちへ』。今回は「YouTuber」をテーマに送る。
* * *
僕の息子が最初に覚えた有名人はYouTuber「ヒカキン」
たくさんの人気YouTuberをマネジメントする「UUUM」という会社が上場して話題になっている。いろんな縁があって僕もその会社に関わらせてもらっているのだが、YouTuberは完全に日本の一つのカルチャーになったのだなと思う。
うちの息子は2歳になり初めて覚えた有名人が「ヒカキン」だ。ヒカキンがなぜ子供に人気なのかをちゃんと語れるテレビ人はあまりいないのではないか。ヒカキンのゲーム実況を2歳の息子と一緒に見ていて気づいたのだが、とにかく滑舌がよく、言葉がわかりやすく、ゲームをやっているときの顔の表情などが多彩。息子もヒカキンの表情で笑う。あれをできる芸能人はなかなかいないだろう。
先日、ある人と飲み屋で口論になった。その人は「ヒカキンなんてうちの子供も見てたけど、中学になったらみんなバカにしてるよ」と。その人の言い分はYouTuber=ヒカキンという考え方。誰だって子供のころに好きだったものは卒業する。あれだけ好きだった仮面ライダーもいつしか急に恋が冷めたように見なくなるし。ヒカキンと話したこともないが、ヒカキン自身は絶対わかってやっていると思う。子供たちに人気でいようと。
僕がそこで言いたかったのは、ヒカキン以外もYouTuberの人気者が増え、いろんなバリエーションが出て、見ている年齢層がだんだん上がっているということ。中高生・大学生が好きなYouTuberもどんどん増えている。
この20年で芸人さんもいろんなタイプが出てきて、ブームから定番になったように、YouTuberもその段階に入った気がする。
驚いた。テレビ見ながらスマホでYouTuberの映像も見れるのにと思っていたのだが、見ているほうは選んでいるようだ。テレビがおもしろいとテレビを見る。ユーザーは「おもしろいほうを選ぶ」。非常にシンプルな答えだが、意外と気づかないし、気づかないフリをしたくなる。
これから2020年に向けて、腕のあるYouTuberはどんどん増えてくると思う。なにがすごいって彼らは自分で編集しているわけで、その編集テクニックもどんどん上がっている。オリンピックがテレビで放送されるとき、彼らはそのオリンピックが行われている東京で、いろいろな企画を考えて動画を作るだろう。そのとき、視聴者が「おもしろい」と思うのはどっちなのか?
そのときに、自分も純粋に「おもしろい」と思われるものを作っていたいと、最近、特に思っている。
※週刊朝日 2017年9月15日号
1970年生まれの団ジュニたちへ特集トップへ