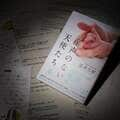■産後うつのリスク高い
都内に住む櫻田智子さん(39)は次女・紗悠(さゆ)ちゃんを死産した翌年に息子(6)を出産した。
「先に生まれた次女より、息子の名前をたくさん呼ぶんだと思うとなんだかさみしくて、しばらくは息子を呼ぶたびに、『紗悠』と心で呼んでいました」
現在は紗悠ちゃんや、その後に流産した璃悠(りゆ)ちゃんのことも家族でよく話題にするので、遠慮せずに息子の名前を呼べるようになった。ただ、ふと「あの子が生きていたら……」と考えることがあるという。
「でも、もし紗悠が生きていたら、息子は生まれてこなかったかもしれないと思うと、複雑な思いもあります」
死産や流産の後は、一般的には医師から「生理を2、3回見送ったら次の妊娠を考えていい」と言われ(帝王切開の場合は1年間あける)、赤ちゃんの死から数カ月で次の子どもを妊娠する人もいる。櫻田さんもメンバーの一人で、赤ちゃんを亡くした家族の心の支援を啓発する当事者グループ「Angie」の共同代表、小原弘美さん(41)はこう話す。
「新しい命を授かることは素晴らしいことですが、心のケアが置き去りになったままだと、死別の悲嘆反応が複雑化するなどして、嘆き悲しむ気持ちが長期にわたって続くことがあります。子どもを失う苦しさを知っているのだから、次子の妊娠中や子育て中につらいと言ってはいけないと思っている人も多く、支援の手が必要だと思います」
日本産婦人科医会の「妊産婦メンタルヘルスケアマニュアル」によると、妊娠中は約10%、産後は10~15%の女性にうつ病がみられる。この「周産期うつ」のリスク因子の一つに「流産や死産の経験」が挙げられている。(編集部・深澤友紀)
※【亡くなった子を激痛に耐えて出産…“レインボーベビー”授かっても癒えない母親の傷】へ続く
※AERA 2020年10月19日号より抜粋
こちらの記事もおすすめ 泣かない息子を産んだ妻…風見しんごが明かす亡き2人の子への思い