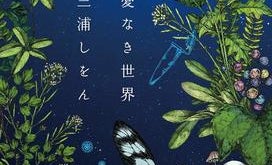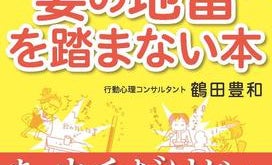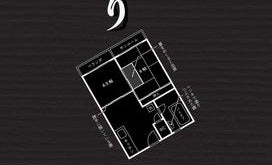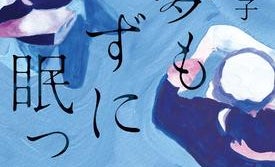蝶々の舞う世界で――マシュー・チョジック『マシューの見てきた世界 人生に退屈しないためのとっておきの21話』
僕はとあるシンポジウムのあとに行われた懇親会で、彼のスマホを渡されて「はーい。チーズ」と言いながら撮影ボタンを連写していた。被写体はそのシンポジウムで議題でもあり登壇者のひとりでもあった小説家の古川日出男さんと、このスマホの持ち主のたぶんアメリカ人の男性だった。彼は見ていてこちらが心地よくなるとびきりのスマイルで古川さんと一緒に記念撮影をした。僕は自分の名刺を渡して、彼にも挨拶してもらって名前を聞いたはずだが、いまいちはっきりしていなかったため、撮影しながらこの人は出版業界の翻訳の人とか、海外からもこのシンポジウムに登壇する翻訳者や大学の先生も来ていたから、その界隈の人なのだろうと勝手に思っていた。翌日あたりに彼からツイッターでフォローされて、マシュー・チョジックという名前で、テレビやラジオにも出てタレント活動をしながら、大学の講師をしつつ出版社も経営している多才な人だと知った。 というのがこの『マシューの見てきた世界 人生に退屈しないためのとっておきの21話』(以下『マシューの見てきた世界))の著者であるマシューさんとの出会いだった。偶然だがいくつか知り合いの共通点があった。この本の帯コメントを書いている園子温監督や、シンポジウムにも登壇されていた柴田元幸さん、あいにくニコラス・ケイジさんと僕は知り合いではないのだが、マシューさんが出演していたNHKラジオ『英語で読む村上春樹』には、園さんのスタッフ「アンカーズ」だった友人が関わっていた、という風に。そして、最初にお会いしたきっかけである古川日出男さん、と勝手に親近感がわいた。実はこのエッセー集を読むきっかけは、知り合いがいて親近感を持ったことだけではなかった。『マシューの見てきた世界』がPヴァインの「ele-king books」というレーベルから刊行されているということも大きかった。 去年『アンダー・ザ・シルバーレイク』という映画を三回映画館に観に行った。内容は都市伝説を扱ったものであり、僕としてはドンピシャだったのだ。そこから連想ゲームが起きた。これを日本でやるなら青山と赤坂を舞台にして、映画同様に日本の芸能史や音楽業界なんかを持ち出して、ヒントや暗号が音楽や映画なんかに潜ませてあるという設定はどうだろうか。例えば、阿久悠の歌詞だとか。主人公が謎を解決するために訪ねる場所には、このミレニアムが始まった時に鳴り響いていたレディオヘッドのアルバム『Kid A』のポスターを見かけることになるというイメージ。 『Kid A』にはもうひとつ双子の兄弟のようなアルバム『Amnesiac』があって、双生児的な世界観というニュアンスが感じられる。双子的な世界、もうひとつの可能性世界という意味ではアメリカのSF作家、フィリップ・K・ディックの小説がある。ディックには双子の妹がいたが、生まれてすぐに亡くなってしまった。彼の小説はネット社会やSNSが当たり前になる世界を予見しているような、ひとりの肉体の中に様々な人格(いくつものアカウントを使い分けるように)があり、個人とは、向き合う世界や人に対して分裂症のように、あるいは多重人格のように世界に接していくことになる予言のように、読めなくもないのだ。 それから『Kid A』と『Amnesiac』を十数年ぶりに改めて聴き始めた。21世紀が来た頃に聴いていた時よりも新鮮でありながらより素晴らしいアルバムに感じられた。きっと、僕自身が変わったこともあるのだろう。そして、世界中で大きな災害が至るところで起きていたし(「氷河期が来るぞ」という歌詞を想起させる)、経済運動も強者や富む者がより豊かになるようにシフトしているからだろう。発売当時はどこか怖さがあった。しかし、現実世界で僕たちはそれを当然のものとして受け入れながら生きてきたからか、鈍感になったのか。それでも音楽は音楽として鳴り響いて、聴き手である僕の身体を揺らしていく。今の自分の感覚と彼らの鳴らす音は以前よりも非常によりシンクロできるものになっていた。何度も何度も聴いた。 マーヴィン・リン著『レディオヘッド/キッドA』という本が「ele-king books」から刊行されていたので読んだ。そして、それから数日後に同じレーベルから出たマーク・フィッシャー著『わが人生の幽霊たちーーうつ病、憑在論、失われた未来』(以下『わが人生の幽霊たち』)という本を書店で棚差しになっているのを発見した。タイトルに惹かれた。このレーベルの書籍には背表紙の部分に「ele-king books」のロゴがあるから、ああ、『レディオヘッド/キッドA』と同じところからだと思った。 すぐには買わずに、後日違う書店で購入する際に著者のマーク・フィッシャーの前作にあたる本『資本主義リアリズム』も一緒に購入した。こちらの本の装丁はレディオヘッド『Hail to the Thief』とそっくりなので、前に何度も見ていて記憶に残っていた。順番通りに『資本主義リアリズム』を読み始めた。そこに書かれていたもので僕がこの10年ぐらいずっと疑問に思っていたことが解けたような気がした。 「当初の見た目(そして希望)とは裏腹に、資本主義リアリズムは、二〇〇八年の信用恐慌によって弱体化されたのではない。(中略)二〇〇八年にたしかに崩壊したのは、一九七〇年代以来、資本蓄積が隠れ蓑にしていたイデオロギー的枠組みである。銀行救済の後、新自由主義はいかなる意味でも信用(クレジット)を失った。しかしこれは、新自由主義が一夜にして消えたということではない。むしろ反対に、その前提は依然として政治経済を席巻するのだが、それはもはや、確固たる促進力をもつイデオロギー的プロジェクトの一環ではなく、惰性的な死に損ないの欠陥(default)として、そこに存在し続けるのだ。」 という箇所を読んで、全世界的に「死に損ないの欠陥」が存在し続けるメタファとしてゾンビ映画やゾンビを題材としたものがミレニアム以降に作られて全世界的にヒットしたのだと僕には思えた。 漫画『アイアムヒーロー』や韓国映画『新感染』もだが、去年は『カメラを止めるな!』のモチーフがゾンビだったこと、そこで描かれるゾンビは現在の社会における信用(クレジット)を失った新自由主義の成れの果てなのかもしれない、と。 『わが人生の幽霊たち』と同じ「ele-king books」から『マシューの見てきた世界』が出ると知ったのは、マシューさんのツイートだったように思う。このエッセーを読むと、彼が出会う人との関係性においてユーモアを忘れずに、人生をたのしんでいることが伝わってくる。それは前述したようなゾンビが蔓延する世界とは真逆なものだろう。 グローバル経済や新自由主義が拡大していけば、個人はより国境や境界線なんかを越えて、より自由にもっと幅広く枠組みなんかを無視して世界中の人と交流していけるはずだった。だが、実際の世界ではそうできない人たちの怨念のようなものが吹き溜まりになって、いろんな悪意や不満がSNSをはじめとして暴発しているように思える。差別主義者が台頭するのはそれも関係しているはずだ。 マシューさんの生き生きとした、国も飛び越えていろんな人と交流する姿は羨ましくもあり、とても読んでいてたのしい気分になる。彼の人との関わり方は、僕らがどこかで期待している、なりたいと願っている人と人との付き合い方のように思えてくる。そこには人への興味と信頼、そして彼の他者への愛と希望があるからだろう。 日本に住んでいる時の視線、世界中を旅したりする時の視線。それらはアメリカ人である彼の視線ではあるけど、当然ながらマシュー・チョジックという個人のものだ。21の物語は彼が体験した日常を綴っている。読んでいると気持ちがあたたかくなってくるのは、彼の人柄があふれでているからだろう、その世界への関わり方と視線が。世界から見た日本、日本から見た世界、どこに立場や足場を置くかで見え方は当然ながら変わってくる。常識も非常識に反転する。当たり前だと思ったことは当たり前ではなくなる世界がある。 マシューさんが出演しているテレビ番組『世界まる見え!テレビ特捜部』でのトレードマークのような蝶ネクタイ。その蝶ネクタイがほんとうの蝶々になって日常をさまざまな角度から捉えていく。そこには現実への興味と自分ではない人たちへの尽きない希望があるのだろう。 蝶々は反転する世界をひらひらとたのしそうに舞いながら、時折花の蜜を吸いにやってくる。その花はいろんな種類があって、味も花びらの色も違う。吸っているとその周辺でちょっとした事件が起きる。蝶々が羽ばたくと舞う鱗粉の鮮やかさのような21話をおたのしみあれ。 文/碇本学(Twitter : @mamaview)