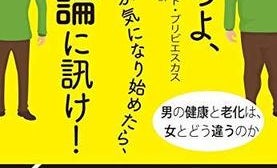
年齢とともに男性のお腹に肉がつくのは悪いことばかりじゃない!?
年末に立て続けにあった忘年会、そして家でゴロゴロしての寝正月......。「ああ、ますますお腹に肉がついてでっぷりしてきたぞ」とお嘆きの男性も多いのではないでしょうか。見た目や健康上の理由から何かと目の敵にされる「肥満」ですが、実はそこには驚くべき進化上のメリットが隠されている、というのが本書『男たちよ、ウエストが気になり始めたら、進化論に訊け!』の著者リチャード・ブリビエスカス氏による主張です。 トンデモ健康本の提唱ならいざ知らず、ブリビエスカス氏はイェール大学の人類学、進化生物学、生態学の教授であり、その著作と研究により数々の賞を受賞しているれっきとした研究者。それだけに本書の内容もあながち間違いではない......どころか、まったく新たなエイジングが見えてくるとして、『ウォール・ストリート・ジャーナル』や『サイコロジー・トゥデイ』など多数メディアで絶賛されているのです。 では老化により筋肉が落ち胴回りの脂肪が増えることは、いったいどんなメリットがあるというのでしょうか? 第3章の「お腹のぜい肉にもメリットあり」では、まずは筆者の考えを述べています。男性は若いころは狩猟や女性をめぐる競争に勝つために筋肉を発達させる進化上の利点があった。けれど、高齢期になり筋肉の一部が脂肪へと変化することで、生殖の機会ではなく「育児」に必要な養育投資を女性に提供するという役割に切り替えられていくということではないかと投げかけています。 そのうえで、第5章では「高年齢男性が老化による身体的な影響を活かして、一夫一婦型のペア形成と父親による養育をおこなう能力を進化させたと提唱したい」とする筆者。そしてこの「年齢によって促進される脂肪の蓄積などの肥満傾向というものが人類の進化過程で活用され、父親の生存率が高まったり、配偶者を探す行動が抑えられたり、父親による養育を支持するホルモン環境への移行が進んだりすること」を「ぽっちゃり父さん仮説」と名付けています。 年齢を重ねるにつれ肥満になっていくことには、実は人類進化上でこのような利点があったとは......。これまでに出会ったことがない(少なくとも私は!)なんとも斬新な考え方ではないでしょうか。 いっぽうでは、高年齢男性が政治権力や経済力を握ることでのデメリットや同性愛の高年齢男性に関する心身の健康といった洞察もおこなわれており、一方的な視点でないのが好ましいところです。 こうして見てみると、ぽっちゃりしているのは悪いことばかりじゃないと皆さんも少しは感じ取れたでしょうか。若いころのズボンが入らなくなってきた男性も、そんな男性を夫に持つ女性も、この本を読んだ後は男性のお腹の脂肪がなんだか愛おしくなってくるかもしれません。













































