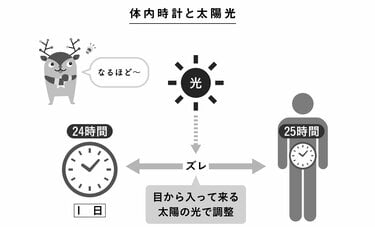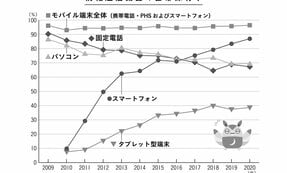【タイプ3】必要なものが足りない「虚証タイプ」で、「気」が足りない人
<気になる症状>
口内炎が治りにくい・繰り返しやすい、疲労感、倦怠感、息切れ、かぜを引きやすい、顔色が白い、食欲不振、軟便、舌の色が淡く腫れぼったい、舌の苔が白い、舌のふちに歯のあとがつく
<改善ポイント>
体内の「気」(エネルギー)は、身体の元気や免疫力の基本。気が不足していると、心身の疲労やだるさを感じやすく、免疫力も落ちてしまいます。
このタイプの口内炎は、気の不足で免疫力が低下し、外邪(風、熱、乾燥などの邪気)の侵入を受けやすくなってしまうことが原因。邪気が体内に停滞すると、熱や乾燥の影響で身体を冷やす潤いが不足してしまいます。結果、体内に余分な熱がこもり、口内炎の炎症が起きやすくなるのです。
対策のポイントは、気の源となる「肺」、「脾胃(ひい)」(胃腸)の働きを良くすること。十分に栄養を摂り、しっかり呼吸をして、体内の気を養いましょう。
<摂り入れたい食材>
「気」を養い、元気をつける食材を。
大豆製品(豆腐、湯葉、納豆など)、いんげん豆、山芋、かぼちゃ、りんご、甘草(かんぞう)など
※温かくて消化の良い食事を。生ものは控えめに!

【タイプ4】必要なものが足りない「虚証タイプ」で、「潤い」が足りない人
<気になる症状>
赤みが少なく微かに痛む口内炎、口内炎を繰り返す・慢性化しやすい、微熱、痩せている、口の乾燥、虫歯になりやすい、便秘気味、舌が少し紅く苔が少ない
<改善ポイント>
身体に潤いを与える「津液(しんえき)」や「血(けつ)」が不足していると、体内の熱を冷ますことができず、熱がこもりやすくなってしまいます。この過剰にこもった熱が、口内炎の炎症を引き起こす原因になります。
身体の潤いは加齢とともに失われていくため、特に更年期を迎える40歳以降の人は要注意。また、食べても太らない痩せ型の人にも多いので、こうした体質の人は若い人でも注意が必要です。その他、月経や慢性的な疾患が潤い不足の原因になることもあります。
日頃から、こまめな水分補給、潤いの多い食材選びなどを心がけ、不足しがちな潤いを積極的に養いましょう。
<摂り入れたい食材>
潤いを生み、熱を冷ます食材を。
はちみつ、干し柿の白い粉、クコの実、レモン、トマト、グレープフルーツ、ぶどう、なし、りんご、卵など
※香辛料は、潤いを消耗するので取り過ぎに注意!

【ポイント】暮らしの口内炎対策
・熱を助長するもの(辛いもの、揚げ物、肉類、酒など)は控えめに。
・食事は“新鮮な野菜たっぷり”を心がけて。
・タバコなどの刺激はなるべく避けること。
・食後のうがいや歯磨きで、口内を清潔に。
・虫歯になったら早めの治療を。
・便通を良くすることも大切。
・できてしまった口内炎には、柿や梅干しを塗るのもおすすめ。

監修:菅沼 栄先生(中医学講師)

本記事は、イスクラ産業株式会社監修の中医学情報サイト「COCOKARA中医学」より、一部改変して転載しました
 AERA dot.編集部
AERA dot.編集部