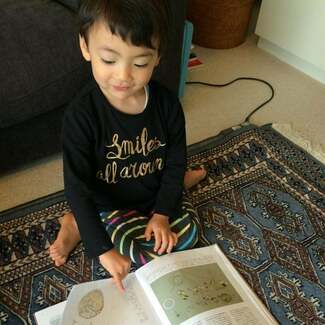■「親ガチャ」という言葉
――この数年はディストピアものの小説が多く発表され、ある種のブームのようにもなっています。この『生を祝う』も、合意出生制度が確立された世界で、そこに天愛会のような団体が存在してしまっていることを考えると、ディストピア小説として読める部分があるのかなという気がします。
李:そうですね。小説にはいろんな読み方がありますので、この小説をディストピアとして読む人がいてもいいし、ある種のユートピアとして読む人もいてもいいと思うんです。私自身はディストピアだと思わないけれども、そう感じる読者がいるのだとすれば、それもまた自由だと思います。
――たしかに、どちらかに決定できないのがこの小説だし、読むたびに感覚が変わっていくところもありました。印象的なのは、「殺意」に対して「産意」という言葉が使われているところで。「殺意も産意もつまるところ、他者を意のままに操りたいという人間の最も根本的な願望の発露にほかならない」と。普段の生活だと、子供が生まれると「おめでとうございます」と言ってしまいますけど、この小説を読んでいると、今まで何に対して「おめでとうございます」と言っていたんだろうと考えさせられました。
李:「産意」という言葉も、私が仕込んだ毒ですね。だから、そこを読んで衝撃を受けてくれたのなら、とても嬉しいです。
――他に「人生という名の無期懲役」という言葉も出てきますが、この言葉にピンとくる人はとても多い気がします。
李:新語・流行語大賞にもノミネートされた「親ガチャ」という言葉もありますね。最近、『出会って5秒でバトル』というアニメを観たんですが、「負けイベ実況プレイ」というエンディングテーマソングの歌詞がすごく面白いんですよ。人生をソーシャルゲームに喩えて、「人生はクソゲーだ」と言っている。そういった感覚は今の時代、わりと共有されていると思います。
――李さんの芥川賞贈呈式のスピーチも、「生まれてこなければよかった」という言葉から始まります。この言葉は、『生を祝う』とも重なっているところはあるんでしょうか?
李:そうですね。ただ、スピーチと重ねて読むと、作者の思いや立ち位置が見えすぎてしまって、それが先入観になってしまうところもあると思うんです。作者の私とはまったく違う立ち位置からこの小説を読むことだって可能だし、出生合意制度なんておぞましいと感じることも可能だし、この小説をディストピア小説として読むこともできる。小説というものは、必ずしも作者と同じ立ち位置で読まなければならないものだとは思っていないんですけれども、この作品については特にそう感じています。この小説にはすごく毒があると思います。ですが、毒がない小説は私の好みではありません。毒にも薬にもなる小説を、これからも書きたいですね。
(2021年10月28日、東京・築地にて/構成:橋本倫史)
 AERA dot.編集部
AERA dot.編集部