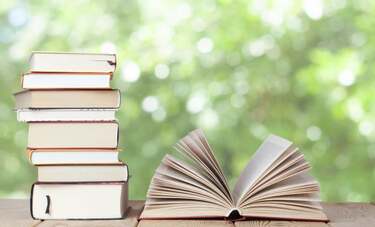李:この二人は、今の世界でもどこにでもあるような人間関係だと思うんです。相手の身体を思いやって、美味しいと思える料理を作る。そういう日常の一コマは、今の世界でも一般的だと思うんですけれども、それが彩華と佳織のあいだにもごく当たり前にある世界を描いたということです。
――二人の関係性はすごくいいものだなと思ったんですけど、その一方で、佳織は彩華より一歳年上で、合意出生制度ができる前に生まれています。佳織の父が、同性愛者の存在を「そんなのは自然に反する性癖だ」と頑なに受け入れない場面も描かれています。現実の世界でも、佳織の父と同じようなことを言う政治家が存在するわけですけども、このあたりはどういう思いで描かれたんでしょう?
李:どういう思いかという質問は、すごく答えづらいですね。同性愛者の子どもと、その親の関係ということでいえば現代の同性愛者のカミングアウト・ストーリーを読んだり聞いたりすると、皆、親に受け入れてもらうことに一生懸命になっている。それは本人にとって切実なことで、非常に大事なことだと思うんですけれども、時に思うんです。当事者はもっとわがままでいいんじゃないか、と。つまり、自分で選んで生まれてきたわけではないのに、セクシュアリティという存在の根源に関わることによって、どうしてあんなにも苦しまなければならないのか。そして、自分の意思をまったく無視して産んだ人に、どうしてそんなに受け入れてもらおうとするのか。そういう思いがどこかにあるんですね。小説の中の世界は、同性婚が当たり前で、同性愛者が非常に尊重されている世界になっている。だからこそ佳織は、あんなにもはっきりと「選べるもんなら、そんな男の子供として生まれたくなかった」と言うことができる。「親に受け入れてもらおうと必死になる」のではなく、「自分を受け入れない親を責める」ということができるのです。今の時代だと、当事者がそれをやると親不孝とされてしまうと思うんですけれども、私はそもそも、そういう今の世界に違和感をおぼえているので。
 AERA dot.編集部
AERA dot.編集部