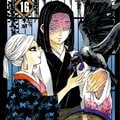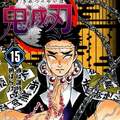翻って日本ではどうだろうか。W杯は4年に1度の大舞台だが、それ以外に監督の働きを精査する場が欠けているのが現実だ。アジア杯は開催年が変更になり、W杯の半年後に行われるようになってしまった。わずか半年で、ある監督に見切りをつけるのも、その後の3年半を任せられると判断するのも難しいだろう。2年目の切れ目には五輪があるが、そのネームバリューは別にして、あくまでも世代別の大会でしかない。仮にA代表と五輪代表の兼務を就任の条件にして、五輪で1度精査するとなった時に、就任する監督の側から納得は得られないだろう。なぜなら、W杯で戦う選手たちと五輪で戦う選手たちは同じではなく、才能の集まる世代だったかどうかに評価が依存するのは承服しがたいものだからだ。
結局、今の日本代表の環境は漫然とした親善試合の連続と、アジアの中でも強豪といえないレベルと対戦するW杯2次予選を戦いながら2年目が終わり、そのあとはW杯最終予選が近づいてタイミングを失い、“なんとなく”4年間を任せることになる。すると、このロシア大会は例外的なことが起こったにしろ、W杯以外の試合に監督の進退問題を判断する強い説得力がないのだ。
そうなってくると、海外から監督を招聘しようとすれば、4年間にわたってクラブの監督市場から離れる覚悟を要求することになる。2年ごとに契約の切れ目と進退が判断されるタイミングがあれば、日本に来る決断へのハードルは下がるかもしれない。もちろん、16年欧州選手権のイタリア代表を率いたアントニオ・コンテ監督のように、優秀な監督がクラブでの指揮を求めて2年で去っていく確率も上がるのだが、結果的に長期政権を生み出す可能性はある。
しかし現状の、まずは4年、次も考えるなら8年というスパンは現役バリバリの外国人監督を招聘し、長期政権を生み出すには悪条件が揃いすぎている。そうした意味でも、外国人監督による長期政権というのは、クラブレベルの指揮を引退する年齢の指揮官、または、悪い言葉を使えば大きなオファーが来ないレベルの監督以外では、実現する可能性がかなり低いだろう。
また、1人の監督に長くチームを任せるとするならば、その条件は「自分で作ったチームを自分で世代交代させられること」だ。