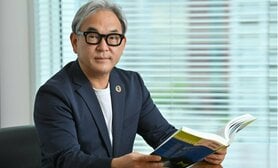「働き盛りの40~50代は仕事で非常に幅広い年代の相手と関わり、家庭では子ども世代とも、高齢の親ともつながっています。40~50代の感染者が増えることで、家庭内でも職場でも感染がさらに広がっていくのです」
感染者の年代が上がったことで重症者数も増える傾向にある。11月14日の時点で、東京都の重症者数は41人と緊急事態宣言解除以降で最多となった。
「感染がさらに高齢者へと広がると、間違いなく重症者も増える。『その先』の対策を急ぐ必要があります」(倉持院長)
一方で、医療の逼迫度合いはどうか。専用病床の占有率は、入院患者全体でみても重症者でみても、10%前後だ。ただし地域や病院によって状況が異なるため、自分が住んでいる地域の状況を確認しておいた方がよい。
医療ガバナンス研究所理事長の上昌広医師は、感染したときの治療方法が確立されてきたことで、感染者数の急増に比べると、重症者や死者の数は比較的抑えられていると話す。
「第1波のときは肺炎を引き起こして亡くなられる方が多かったのですが、重症肺炎の予防になるステロイドホルモンなどによる管理の仕方がうまくなったので、第2波からは肺炎の死者が減って、致死率もぐっと減りました。治療がうまくなったと判断してもよいでしょう」
上医師によれば、ステロイドを使うと免疫が抑制されるため、軽症者の病状を悪化させる可能性があるものの、重症肺炎の予防になる点で、有効な治療方法の一つになっている。
「これまでの世界の医学研究で、コロナ感染症の致死率を明らかに減らしたのはステロイドホルモンだけとされています。その使い方が上手になったというのは、非常に大きいと思います」
(編集部・小田健司、小長光哲郎、大平誠、福井しほ)
※AERA 2020年11月30日号より抜粋
こちらの記事もおすすめ 院内感染「どの病院で起きてもおかしくない」 完全には防ぎきれない意外な理由とは



![AERA (アエラ) 2020年 11/30 号【表紙: JO1 】 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51CEGn5Ml-L._SL500_.jpg)