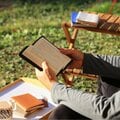「TJARの参加要件は簡単ではないけれど、バリバリのアスリートである必要はなく、『努力すればできるかも』と思える課題です。参加者は『すごい人』だけれど頑張れば追い付けそうな存在なんです。ちょっと上の目標として、多くの人を引き付けているのだと思います」
■ルール改正で過酷に
TJARでは今年、ひとつの大きなルール改正があった。これまでは午前5時~午後6時に限り認められてきた「山小屋での食事や買い物」が禁止になったのだ(ふもとのコンビニなどは利用可)。選手が持たなければならない食料は格段に増え、補給方法の検討も求められる。
「自分で食べるものは自分で持っていくのが登山の原点。しかし、最近のTJARでは完走のための戦略として『いかに山小屋を使うか』が重視されていると感じることがありました。ルールでは問題ないけれど、方向性が変わってきたと感じていました。レースの原点を感じられるように、より挑戦しがいのある場になるように、ルール改正を決めました」(飯島さん)
前出の望月さんも、このルール改正に賛成する。望月さんは今大会には出場しないが、前回18年大会では、この改正ルールよりもさらに過酷な、ふもとのコンビニすら利用しない「無補給」でレースに挑んだ。
「山小屋を使っていいとなればそこに甘えてしまう。それができなくなることで、より自分の限界にチャレンジできます。TJARは速く走ることだけが目的じゃないんです。同志とともに力を出し尽くして海を目指す、その原点がより感じられるレースになると思います」
400キロを超す道のりも、1歩踏み出せばその分ゴールに近づいていく。そのことを実感できるのもTJARのよさだと望月さんは言う。すでに、来年の開催に向けた準備が始まっている。(編集部・川口穣)
※AERA 2021年8月16日-8月23日合併号の内容を一部加筆・修正