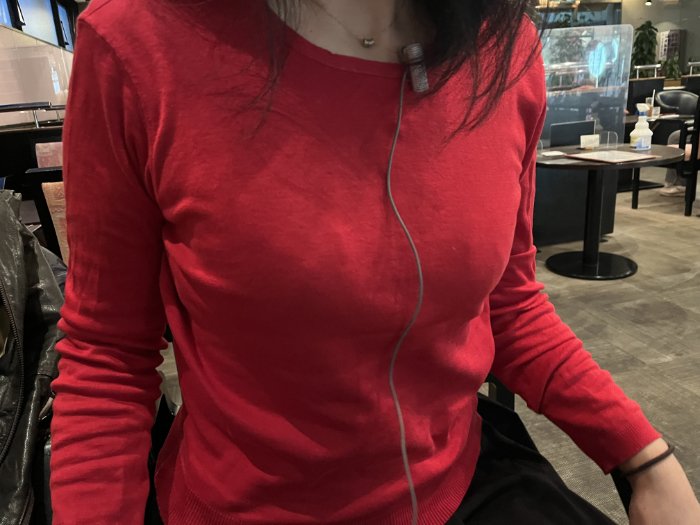
「私は、『ワキガみたい』と思ってます。自分の体臭なんだけど、ちょっとにおいが強くて嫌だな、みたいな。でも、フェロモンって珍重される場面もあるし、もしかして私の存在理由の1つかもしれないから無下にもできない」
もう1人の自分に、随分な言いようである。
「たぶん、私が『声』の存在を認めていないから、向こうも強く当たるんでしょうね。『いてくれてありがとう。あなたがいるから私はあるよ』とか思っていないから」
編集の仕事は幸せじゃない
もっとも、自分に厳しいのは「声」だけでなく、綾子さん自身も同じだった。
ため息をつくように、こんなことを言う。
「幸せじゃないんですよ、編集の仕事って。もちろん、私にとっては大切な仕事ですけどね。原稿をもらって、あとは校正とか作業的なことが続くと、『次の企画を探さなきゃ』って焦る。一段落すると不安になるというか。『これでいいんだ』って思えることがないんです」
自分に合格点をつけられない
だが、よくよく聞くと、それは今に始まったことではなかった。
「子どものころから、常に振り回されている感じがありますね。『これがやりたい』って自分で決めて、ゴールに向かっているという実感があまりない。『自分はよくできた』って思ったことがないんです」
つまり綾子さんは、何を得ても自分に合格点をつけられないのである。一体、どうしてそうなってしまったのだろう。
「わからないけど、親かな」
達観したように、綾子さんは言った。母との関係がよくなかったようだ。
「こうしちゃいけない、ああしちゃいけないというのが多くて、過干渉ではありますね。なんでも否定されるから、自分の意思で決めるっていうことが難しかったです」
クリスチャンの母がカラオケを「ふしだら」
綾子さんの母はクリスチャンで、もともとキリスト教系の女子校で教師をしていた。結婚して専業主婦になってからは、学校での教育を、そのまま子どもたちにも行っていたようだ。
「女性は清く正しくみたいなね。たとえば、ちょっと浮ついた女友だちと一緒にいるだけで嫌がられる。当時唯一の盛り場だった駅前の西友にも『行ってはいけない』と言われていたし、高校生になって、男の子も参加するカラオケにみんなで行くとかいうと、『ふしだら』と言われたり。大学生のころにアメリカ人の男性とお付き合いしたことがあって、彼の仕事の同僚たちも含めてみんなでニューヨークへ遊びに行くってなったときは、親がすごく焦って『成田空港で体を張ってでも阻止する』って言われましたね」




































