こうみてくると、葬儀はどんどん小規模化、消滅の傾向にある。
20年ほど前、葬祭業者の経営者たちの勉強会に呼んでいただいたことがあるが、「これからの葬儀は小規模化していくだろう」と話したら、「これからは老後が長くなり、活動的な高齢者が増えるので、葬儀の参列者は増えるはずだ」と、ある経営者に反論された。結果、どうだろうか。
葬儀の意味合いがプライベートな儀式へと変わった
私の説が正しかったなどと言いたいのではなく、この20年間で、葬儀の意味合いが、社会的な儀式から、身内を中心としたプライベートな儀式へと変わったのだ。これまでは、お葬式は景気が良くなれば派手になり、景気が悪くなると地味になるという経緯をたどっていたのだが、2000年以降は、景気とは関係なく、お葬式をおこなう意味が変容してきたといえる。
しかも、お葬式に参列する人たちと故人との関係がどんどん密になっているのが最近の傾向だ。義理で参列する外野が少なくなり、参列者は血縁者が中心となっている。しかし一概に血縁者といっても、それが意識の上で、「家族」であるとは限らない。例えば、家族葬という言葉はすっかり市民権を得たが、これは、具体的には誰が参列するお葬式だろうか。
私の知り合いは、末期のがんで闘病していた弟のお見舞いに、毎月病院へ行っていたというが、ある日、弟の妻から「故人の遺志により、家族葬ですませた」というはがきが届き、驚愕したという。前の月に病院へ見舞ったが、その後、体調が急変し、亡くなったらしい。知り合いは、弟の訃報をこんな形で知らされたことよりも、「自分は家族葬に参列する立場ではないのか?」ということに納得がいかなかったそうだ。
最近では、「亡くなった祖父母を家族葬でするから」と、孫が参列しないケースもある。実際、私が大学の講義のなかで家族をテーマに取り上げると、多くの学生は「おじいちゃんやおばあちゃんは家族ではない」という。先日は、「飼っているメダカは家族だけれど、祖父母は親戚」だと発言した学生がいて、びっくりした。一緒に住んでいる(いた)かどうかが、自分にとっての家族か、親戚かの分かれ目なのだろう。三世代同居が減少し、祖父母とは年に数回会うだけの関係になると、祖父母は、おじやおばと同じく、親戚であるという感覚になっても、不思議ではない。
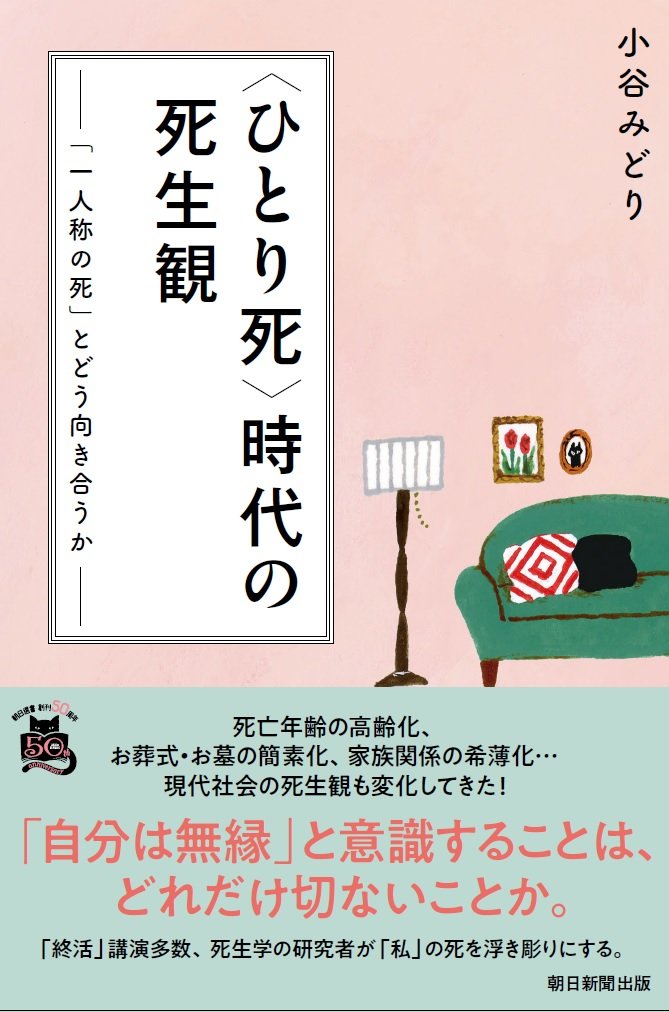
※朝日選書『〈ひとり死〉時代の死生観 「一人称の死」とどう向き合うか』(朝日新聞出版)から一部抜粋
こちらの記事もおすすめ ライフプランに「死」がない 『〈ひとり死〉時代の死生観』著の死生学者が30年前に感じた違和感






































