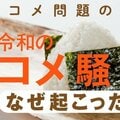早場米の収穫まであと1カ月ほど、消費者が気になるのは今年の新米の価格だが、昨年より値上がりするのはほぼ確実だという。集荷業者による米の買い付け競争が激しさを増しているからだ。
【コメ不足の真相】「令和のコメ騒動」はなぜ起こったか【徹底解説】
* * *
8月には早場米の買い付け
6月下旬、千葉県匝瑳(そうさ)市に広がる水田では、青々とした稲が風に揺れていた。8月中旬になると、栄営農組合の100ヘクタールもの水田では稲の刈り取りが一斉に始まるという。
「いよいよ『本土決戦』がスタートする」
同組合の伊藤秀雄顧問は鋭い目つきでこう語った。
温暖な気候の千葉県は、「早場米」の産地として知られ、全国8位、約27万トンの収穫量を誇る(2024年)。8月になると東日本を中心に全国から集荷業者が米の買い付けに訪れる。
千葉の「価格」が全国に影響
「沖縄や九州の早場米は収穫量が少ないので、事実上、米の出荷はここ千葉県から始まります。ここで安値が形成されてしまうと、他の地域に波及する。大きな責任のある立場にあると自覚しています」(伊藤さん)
「本土決戦」とは穏やかな表現ではないが、米の買い取り価格は米農家の収入に直結している。買い取り価格が下がれば、農家の生活は苦しくなる。それだけに、切実な思いがある。

ほとんどの農家は採算割れ
23年までの10年間、全国的な米の買い取り(相対取引)価格はおおむね60キロ1万2000~1万6000円の間で推移してきた。生産コストは同1万5000~1万6000円なので、ほとんどの米農家は採算割れの状態に陥っていた。
1970年に約466万戸あった米農家は、2020年には約70万戸と、約6分の1にまで減少した。伊藤さんは、こう語る。
「私が55年前に就農したころは、1ヘクタールほどの水田で家族を養い普通に生活することができました。ところが、米価がどんどん下がり、米農家は軒並み赤字になった。こんな状態でどうして後継者が育つでしょうか」
「全農」にモノ申す理由
農家が出荷する米の価格について、大きな影響力を持ってきたのが全国農業協同組合連合会(JA全農)だ。
「だからこそ、私は『やい、全農』と県本部に悪態をついてきました。『米を安値で買い叩いてきたあなた方が元凶だ』と」(同)