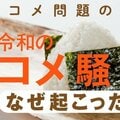JAが米価に大きな影響力
伊藤さんが「全農」をこう評する理由は、一部のSNSで言われているような「闇の中間業者」だからではない。農家からの米の買い取り価格の設定に大きな影響力を持ってきたからだ。
農家が収穫した米は、集荷業者に出荷され、卸売業者が精米して小売店の店頭に並ぶ。農家から米を集荷する業者の一つが、全国各地にある農業協同組合(JA)だ。
JAは集荷した米の等級検査をする際、一般的に「概算金」と呼ばれる仮払金を農家に支払う。全国の概算金はおおむね60キロ1万1000~1万3000円の間で推移してきたが、この概算金の額を決めるのがJA全農の県本部・経済連なのだ。JAが卸売業者に米を販売する金額を「相対取引価格」と呼ぶが、この相対取引価格から概算金と経費を差し引いた金額を、JAは農家に追い払いする。
JA以外の集荷業者は、農家に概算金が提示されるのを待って、そこに「ほんの少し色をつけ、60キロあたり500円玉1個、千円札1枚を加算して買っていく」(同)。
つまり、「概算金」が基準として大きな影響力を持っているということだ。
「国」も米を安値に誘導してきた
伊藤さんはもう一つ、「国」も米価に影響を与えてきたと指摘する。この「概算金」の土台となってきたのが、政府備蓄米の買い入れ価格だという。価格は入札で決まるが、その基準は市場価格を参考に決められる。毎年、備蓄米として政府が買い入れる20万トンは、全国トップクラスの卸売業者の年間取扱量に匹敵する。
「これほど大量に米が取引されることはまずないし、事実上、国が決めた価格だから、価格支配力は大きい。それが概算金の指標になっていると感じてきた。国は備蓄米の買い入れ価格によって、米価を安値誘導してきたともいえると考えています」(同)
「令和の米騒動」から状況が変化、買い負けるJA
けれども、いわゆる「令和の米騒動」が起こってから、状況が変わった。「これまではJAが提示する『概算金』が米を売り渡す際の基準でしたが、昨年からそれが変わったんです」と、福島県天栄村の米農家・吉成邦市さんは語る。
昨年から米の買い付け競争が激しさを増し、予定していた集荷量を達成できないJAが全国で続出しているという。
昨年9月、吉成さんは60キロ1万8000円(概算金)でJAに米を出荷した。
「その前に、他の集荷業者は2万円台の値段をつけてきた。それで、JA以外の集荷業者に流れた農家は多い。つまり、JAは他の集荷業者を甘く見て、失敗したんです」(吉成さん)