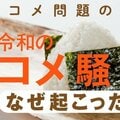「新規就農は可能性ゼロ」
「稲作で新規就農なんて、まったく無茶な話で、可能性ゼロですよ」(同)
50歳代以下の農業従事者の割合は、稲作は11.3%、露地野菜は26.0%、施設野菜は36.0%、果樹は20.6%で、米作りをする若者は少ない(20年)。最大の壁は、農業機械を購入する費用が用意できないことではなく、水田を入手できないことだという。
「米農家として経営を成り立たせるには一定面積以上の水田を借りなければならない。米農家は先祖代々受け継いだ土地を荒らされたくない。だから、知らない人には土地を貸さない。『この人なら絶対に大丈夫』という人にしか、水田は集まらない」(同)
米農家の生々しい現実
吉成さんは「一人でどこまで作付面積を増やせるか」挑戦してきたが、10ヘクタールが限界だという。天栄村の竜田川流域の水田はかんがい施設が未整備で、天水(雨水)に頼った稲作が行われている。
「関東平野の利根川下流域の水田ではバルブをひねれば水がバーッと出ますが、この周辺では水路に土のうを積んで水田に水を入れなければならない。使える水が限られているので、こまめに管理しなければならない。労力がかかるうえ、我田引水ということわざもあるように、引く水量の調整は他の米農家にものすごく気をつかう」(同)
吉成さんが生まれる少し前、天栄村では、水争いが原因で凄惨な殺人事件が起きたという。
「米農家にとってそれほど水は重要で、水争いはそれほど怖い。全国の耕地面積の約4割はこのような『中山間地域』にあるのに、生々しい米農家の現実が国には全く伝わっていない」(同)
「団塊の世代」の稲作農家が消えていく
これまでは離農する人がいても、水田を引き受けてくれる農家がいた。しかし、最近は断る人も出てきたという。
「所有する水田が散らばってしまい、遠くの田んぼは管理しきれない。そこまで行って帰ってくるだけで、燃料代もばかにならない。仕方ないことですが、米を作りづらい水田は引き受け手が見つからず、放棄される。村の風景も変わっていくと思います」(同)
今年、いわゆる「団塊の世代」は全員が75歳以上になった。
「これまで団塊の世代の農家が頑張って米作りを支えてきた。これから米農家は急激に減るでしょう。国のどんなに偉い人が『増産しろ』と言っても、現状では無理ですよ」(同)
そう言う吉成さんの表情は悲しげにすら見えた。
作り手の切実な事情を、政治家の誰が知っているのだろうか。
(AERA編集部・米倉昭仁)
こちらの記事もおすすめ 【もっと読む】新米は今年も「値上がり」必至 生産者ですら「5キロ4000円台は高い…」とため息 買い付け競争激化に危機感を抱くワケ