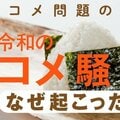「今後は米を増産する」。国は、半世紀以上にわたって実質的に続けてきた「減反」政策を転換した。しかし、農家からは「いまさら増産は無理」という声が上がっている。何が起こっているのか。
【コメ不足のカラクリ】「令和のコメ騒動」はなぜ起こったか【徹底解説】
* * *
「現場を知らない」と怒り
「政府が『米を増産しろ』と言いさえすれば、農家が直ちに増産すると思ったら、大違いです。現場を知らない、机上の空論ですよ」
憤まんやるかたない口調で語るのは、福島県天栄村の米農家・吉成邦市さんだ。
政府は今年4月、中長期的な農政の指針となる「食料・農業・農村基本計画」を閣議決定。目玉となるのが米農政の大転換で、1970年代から続いてきた事実上の「減反」から、増産に舵を切る。23年は791万トンだった米の生産量を、30年には818万トンに増やす方針だ。
石破茂首相は7月1日、政府の「米の安定供給等実現関係閣僚会議」で、「令和7年産から増産を進めていく。不安なく増産に取り組める新たな米政策に転換する」と表明した。
米農家の約6割が70歳以上
だが、米を増産するには作付面積を増やさねばならず、増産規模に合わせた新たな農業機械も必要になる。吉成さんはこう話す。
「高齢化が進む米農家が、増産を目指していまさら農業機械を買えるわけがないでしょう。農機がどれほど高額か、知っていますか」
現在、個人経営の米農家の平均年齢は71.1歳(2020年)で、70歳以上が58.9%を占める。
3000万円を投資、減価償却費だけで年300万円
吉成さんは同村の元職員で、20年あまり農政を担当した。定年前に退職し、2ヘクタールから米農家を始めた際、約3千万円を投資してトラクターや田植え機、コンバインなどの農業機械を買い揃えた。退職金だけでは足りず、JAからの借入金もつぎ込んだ。減価償却費だけで年間約300万円にもなるという。
「米農家になったときは59歳だったので、これだけの金額を投資できた。66歳の今だったら、無理でしょう。投資した費用が回収できるか心配で、気持ちももたない」(吉成さん)
米農家を始める際、どうすれば経営が成り立つか、念入りに計算した。米の売り上げから農業機械や肥料、農薬、燃料などの資材代を差し引くと、損益分岐点となる作付面積は3ヘクタールだった。