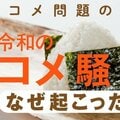大規模でないと儲けが出ない
「つまり、米農家は大規模にやらないと、儲けが出ないんです」(同)
全国の平均作付面積は1.8ヘクタールだが、その規模の農家の場合、生産コストは60キロ1万5944円(23年)。これに対し、農家の米の売値(23年11月の相対取引価格)は同1万5240円で、シンプルに赤字だ。15ヘクタール以上の農家であれば、生産コストは同1万1350円に下がる。
ちなみに、20年時点の全国の米農家(水稲作付経営体)71万3792軒のうち、作付面積が2ヘクタール未満の小規模農家は全体の81%。つまり、米農家のほとんどが「赤字経営」なのだという。
農機が壊れるまで作り続けるのが得
「ただ、数字の上では赤字ですが、小規模農家はトラクターを30年くらい使う(法定耐用年数は原則7年)。そうすると、肥料や農薬、燃料などの資材代を差し引いても多少は儲けが出る。であれば、農業機械が壊れるまでは米を作り続けたほうが得になる」(同)
裏返せば、「年をとってトラクターが壊れても、400万円を支払って買い替えない」。機械が壊れたら、そこで米作りを引退する小規模農家は多いという。そんな小規模農家が今後、作付面積を増やしたり、リスクを取って農業機械を新たに購入することはまずないだろう。
9割が「経営が苦しい」
今年5月に産直通販サイト「食べチョク」を運営する株式会社ビビッドガーデンが行ったアンケート「米の生産に関する実態調査 第2弾」によると、米農家の9割が「経営が苦しい」と回答した(回答人数は121人。生産規模は1ヘクタール未満21%、1~5ヘクタール未満36%、5ヘクタール以上43%)。内訳は、「廃業を考えるほど苦しい」13.1%、「とても苦しい」49.2%、「少し苦しい」27.9%、「その他」9.8%だった。
後継者のいる農家は3、4人
吉成さんは「農業機械が壊れた」「体が動かなくなった」などの理由で米作りを引退した農家から、水田を購入したり借り受けたりして、作付面積を10ヘクタールまで増やしてきた。
20年ほど前、天栄村の米農家は600軒ほどあったが、現在は約350軒に減少した。そのうち、吉成さんのように、稲作を主な収入源とする「主業農家」はたった10軒ほどしかないという。
「後継者不足も深刻で、10軒のうち、後継者のいる米農家はうちも含めて3、4人しかいません」(同)
高齢化が進むなか、若手は不可欠だ。米作りの世界に飛び込んでくる若手はいないのか。