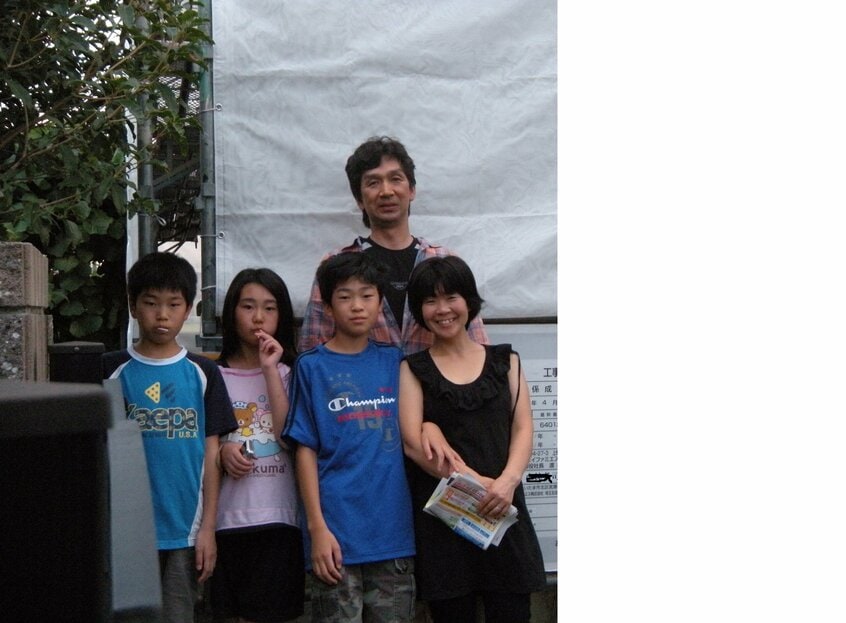
明美さんは13年、会社が異動などの対策を取らなかったことは安全配慮義務違反に当たるなどとして、さいたま地裁に提訴。16年に日本郵便が解決金を支払うなど和解に至った。その後、労災も認められ、会社側は明美さんへ謝罪し「二度とこのようなことは起こらないようにする」と約束したという。
いま郵便局では、お立ち台も自爆営業も基本的にはなくなっている。しかし、その後も在職中の死亡が相次いでいる。
先の倉林さんは、「郵便局に残るゆがんだ企業風土が問題」と指摘する。
「官僚時代の上意下達の硬直した体制を変えられず、そこに過度な競争を強いるあやまった民間意識が注ぎ込まれました。それがいまだに改善されていません」
深夜勤務は拘束時間が長い
さらに、非正規社員の増加も突然死との関連が指摘される。
07年の郵政民営化以降、郵便局は収益性を重視し人件費を抑えるため、非正規社員の活用が進んだ。23年度、日本郵政グループ4社の社員総数は約37万人で、このうち非正規社員は約45%の約16万人を占める。
非正規社員は正社員と比べ給与が低い。そこで、郵便局では賃金の深夜割増がつく深夜勤務に就くケースが多い。だが深夜勤務は拘束時間が長く、健康への影響が懸念されている。
家族会によれば、昨年は1年だけで全国で5件の死亡事例が確認されている。そのうち3件は、東京都江東区の新東京郵便局での深夜勤の非正規社員だった。亡くなった局員は勤務年数10〜20年で、特に持病はなかったという。
「深夜営業以外にも、郵便局は非正規の労働者に支えられています。しかしそのため、かつてのように労働者が団結したり助け合ったりする職場の絆が崩れ、つらくても声を上げることもできなくなっています」(倉林さん)



































