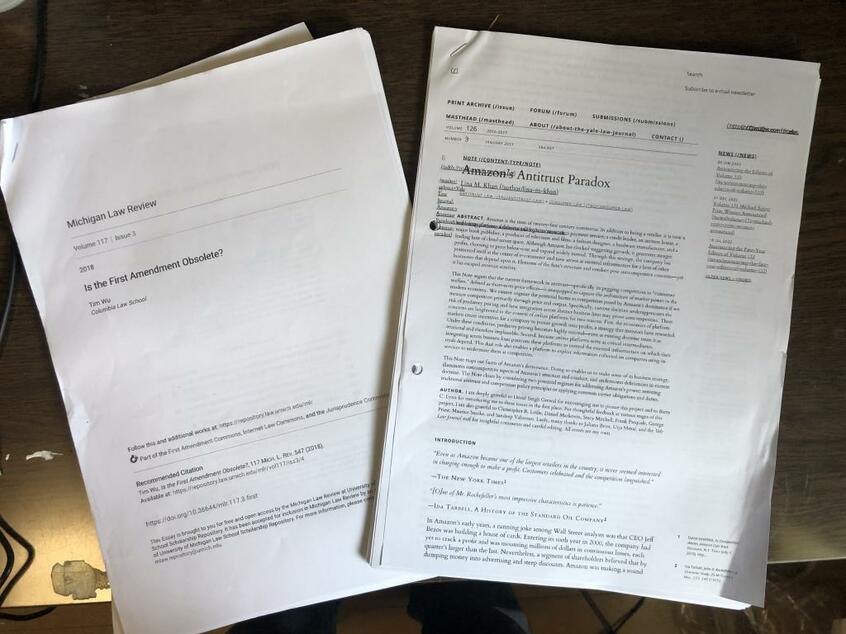
ここで、ヤフーはプラットフォーマーの地位から滑り落ちる危機を迎えるのである。PCの時代は、ブラウザーを立ち上げた最初の画面に、ヤフーを登録してもらい、ショッピングや交通情報、ニュース、旅行など様々なサービスをこのサイト内で完結するように提供すれば、それだけ、ユーザーの滞在時間も長く、それが広告料金に結びついていた。
ところが、スマートフォンの場合、ヤフーはアプリのひとつになってしまった。スマートフォンのプラットフォーマーはOSを提供しているアップルであり、グーグルだ。アプリストアに提供する側は、3割なりのしょば代をアップルに払ってアプリという出店をだす。
ヤフーとその親会社であるソフトバンクは、どうすればそうした状況のなかで、スマホでも、プラットフォーマーとしての地位を獲得できるかを当時考えた。
グーグルやアップルに対抗してOSをつくり、それを普及させるというのは現実的ではない。そこでソフトバンクの孫正義が着目していたのが、決済アプリだった。
孫は、1999年の夏、ジャック・マーに会い、米国のドットコムバブル崩壊で、潰れかかっていたアリババに3000万ドルを出資、ソフトバンクはアリババの筆頭株主になる。アリババは、2010年代に、独自の決済アプリ「アリペイ」をつくりあげていた。中国の小売はみな現金からQRコード決済を利用したアリペイでの決済に置き換わっていくなかで、このアプリは、余額宝とよばれる投資信託やホテル・交通機関の予約、EC、さらには税金の納付まで様々なサービスの入口となっていく。個人個人の信用格付けを点数化する芝麻信用とセットで使われ、中国の人々はまずこのスーパーアプリ「アリペイ」を開いて生活を始めるようになった。
つまりスマートフォンのOSをとらずとも、アリババは、決済アプリでスマートフォンでのプラットフォーマーの地位を確立したのである。
それを日本に移植しようとしたのが、ヤフーとソフトバンクが2018年10月に始めた「ペイペイ」ということになる。現在の登録者数が5000万人、QRコード決済でのシェアが6割というから、プラットフォームとしての地位を築きつつある、ということになる。





































