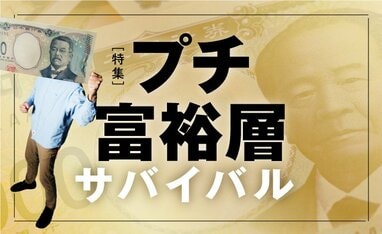それは米国の代表的なIT企業のグーグルでも同様だった。もともとIT技術者のマクマートリーさんは直前に働いていたアマゾンでも、環境問題に取り組む運動をしていたが、グーグル社員が同時期さかんに取り組んでいた社会運動にひかれ、引っ越しのタイミングで、グーグルに転職した。グーグルでは2011年、経営に対する意見を伝えながら、働き手の労働条件を改善する運動が始まった。経営に対して、当時主流だった実名でしか登録できないITサービスは、人によっては危険を伴うのでやめるべきだと進言した。
「戦争に使われる技術を開発しない」という約束は……
2015年には賃金の不平等が男女や人種で生まれていないかを確認し、2018年には、セクハラをおこなった幹部が解雇されず9千万ドルの退職パッケージが与えられたことに抗議するため、従業員が「真の変革のためのウォークアウト」という職場から歩いて出るという行動にも出た。国防総省からAI開発を受注したことに対して、今後は戦争に使われる技術を開発しないことを約束するよう求めるといった運動を積み重ねた。こうしてグーグルでは、毎年のようにデモを繰り返したが、その時々の一過性で終わってしまった。こうした人々と社会運動が培った力を溜め、つなげていくための枠組みとして、労組という形が最適だったのだという。
ただトランプ政権下で、こうして積み重ねられてきた成果が方針転換を余儀なくされている。2025年1月にドナルド・トランプ大統領が2期目に就くと、グーグルは会社の方針としてDEI(ダイバーシティ・エクイティー・インクルージョン)など多様性を考慮した採用目標を廃止したほか、AIを兵器や監視に応用しないという方針を削除した。これに対し、AWUはAI倫理について、委員長名で同年2月4日、次のような声明を出した。
「グーグルが、戦争ビジネスに参入すべきではないと従業員が長年思ってきたにもかかわらず、従業員や広く一般からの意見を聞くこともなく、AI技術の倫理的使用へのコミットメントを取り下げたことは、深く憂慮すべきことである」 (グーグルソフトウェアエンジニア兼AWU-CWA会長 パルル・クール)