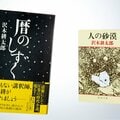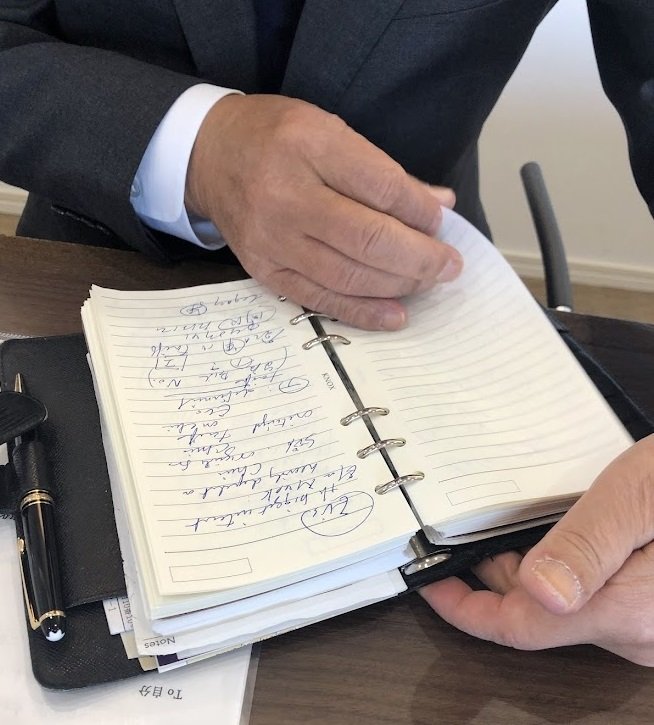
日米双方の当事者にあたる
この本は、記述の論拠を、すべて章末にあげている。このトランプと金正恩の真剣勝負のくだりには(106)の番号がふられ、章末を確認すると、次のように記されている。
〈106 元官邸スタッフ、2021年4月21日/安倍晋三、2021年5月14日/元ホワイトハウス幹部、2023年5月2日/官邸幹部、2024年3月7日/元ホワイトハウス高官、2024年3月9日〉
つまり、匿名の官邸スタッフから拾った話を、翌月に安倍晋三本人に確認をし、さらに米国側の交渉当事者二人にも確認をして、この記述をしているのだ。
安倍総理番と言われた記者は各社にいて、こうした人たちは安倍の死後も、それぞれに安倍首相について書いたり、話をしたりしている。が、このように、相対する米国の政権当事者に直接取材ができているのは、船橋しかいない。
しかし、いったいどうやって?
記者クラブでもない縁故でもない
船橋が、朝日新聞の主筆をひいて退社したのが、2010年12月。この退社の日に、文藝春秋の編集者だった私は、電話をもらっている。その日朝日を退社すること、社から電話をしていることを告げたあとに、船橋は、月刊文藝春秋でコラムを連載できないか、と聞いてきたのだった。
「ホームグラウンドとしてのコラムをもっていることで、ジャーナリストとして今後も活動していける」
そう言った。当時の編集長に紹介して「新世界地政学」の2ページのコラムの連載が始まった。
ここまでだったらば、ごく常識的なコースと言えるだろう。しかし、特筆すべきは、その後2011年3月に東日本大震災が起こり、福島第一原発の事故がおこる中で、その事故の検証を民間のシンクタンクをたちあげて行ったことだ。
「2011年5月に、近藤正晃ジェームスさんと話して、これは政府だけに調査をまかせていてはいけない。民間の手で調査をする必要があるともりあがった。しかし、お金がかかる。朝日時代に私は三つ米国のシンクタンクにいた経験があった。それで、シンクタンクを立ち上げようということになった」(船橋)
お金は民間から集めるが、ひとつの企業や団体から25パーセント以上の拠出をうけず独立性を担保する、というのも、アメリカのシンクタンクにならったそうだ。