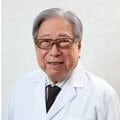厚生労働省の「健康日本21(第三次)」では、低栄養傾向の高齢者は要介護リスクや総死亡リスクが統計学的にみて有意に高くなるとして、低栄養傾向の高齢者の減少を目標に掲げている。
なお別の研究では、やせた人のほうが肥満の人より死亡率が高い傾向にあることも報告されている(*)。

高齢になると、若いころより体の筋肉や水分が減ってくるため、低栄養になると、次に示したような症状が起こりやすくなる。
- 認知機能低下
- 気力がなくなる
- 免疫力や体力の低下
- 病気にかかりやすい
- 筋肉量や筋力の低下
- 骨量減少
- 骨折の危険増
高齢者は消化機能が落ちていて栄養を十分に吸収できない
筋肉量や筋力の低下は、サルコペニア、フレイルといった病名で知られる通り、要介護などにつながる問題になっている。骨量減少は、筋肉量や筋力の低下から転倒しやすくなり、骨折の危険が増す。また、サルコペニア、フレイルは、活動度や消費エネルギーの減少、食欲低下をもたらす。それでさらに食べる量が減り、低栄養状態を促進させるという悪循環に陥るのだ。
高齢者にとっては、栄養バランスよく食べる以前に、欠乏しがちなエネルギーやたんぱく質を意識的にとるようにするほうが大事なのだ。
しかし、これがなかなか難しい。高齢者になると、食が細くなる。消費エネルギーが少ないと食欲もわかない。これはあとで述べる「生きがい」が食欲に関わってくると思っている。
また、それなりに量を食べられたとしても、高齢者は消化機能が落ちていて栄養を十分に吸収できない。若いころは食べる量を減らしたり、食欲を抑えたりすることに注力していた人も多いと思うが、高齢者は逆に意識して食べなければいけない。人間も動物なので、食べられなくなったら終わりなのだ。
サルコペニアなどの筋肉の研究の進歩により、わかってきたことは、高齢者では高たんぱくの食事をとらなければ、筋肉が減る一方であるということ。そして、肉が最も効率的にたんぱく質を摂取できるということだ。
一昔前までは、「高齢者は食べられるだけで十分である。肉はあまり食べないほうがいい」といわれていたが、現在は肉を食べることが推奨されている。