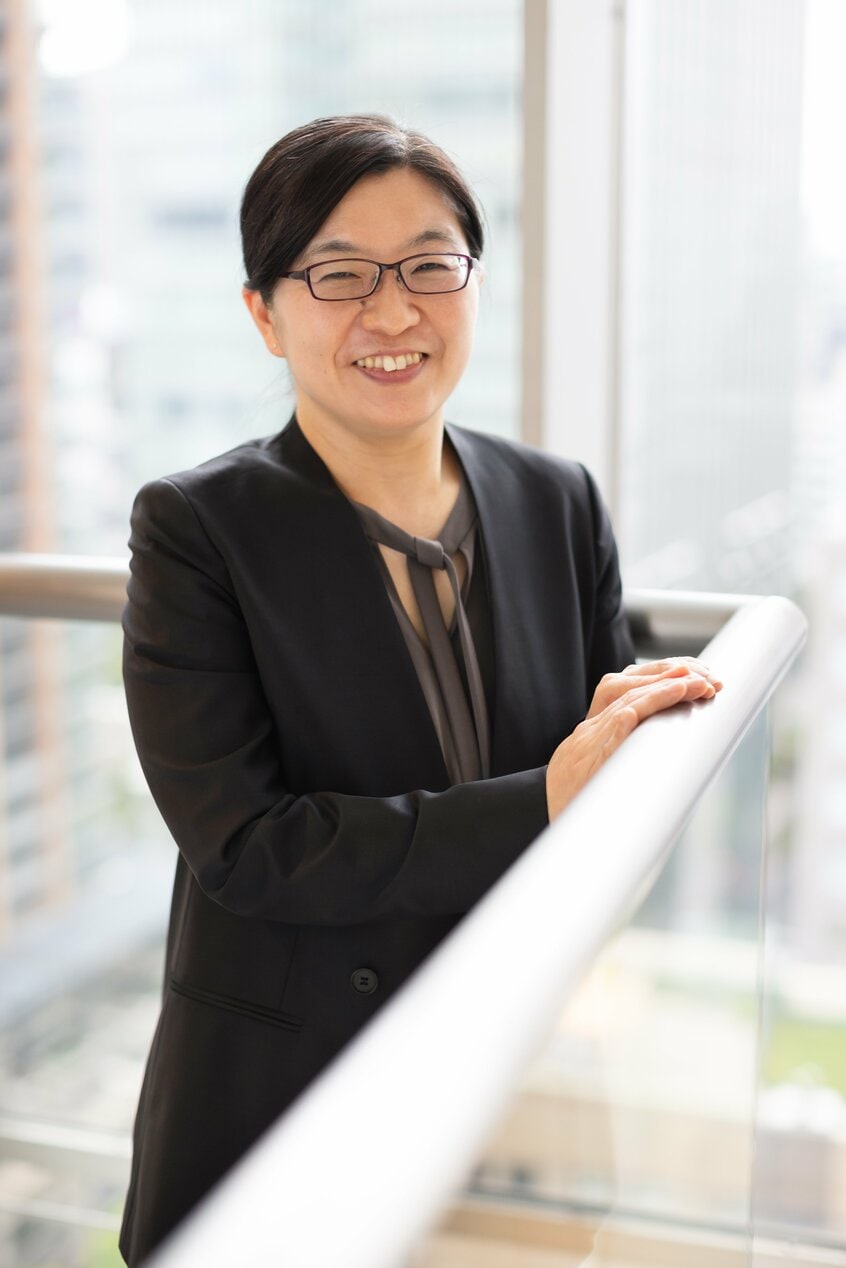
AERAで連載中の「この人のこの本」では、いま読んでおくべき一冊を取り上げ、そこに込めた思いや舞台裏を著者にインタビュー。
歌舞伎とともに変遷・発展した歌舞伎音楽は、長唄、竹本(義太夫節)、常磐津節、清元節といった舞踊音楽や情景描写・人物描写など多様な機能を担う黒御簾音楽など、独自の豊潤な世界を築いてきた。本書は歌舞伎音楽のジャンルと特徴、使用楽器、歴史から、歌舞伎をより深く楽しむうえで知っておきたい情報を網羅。具体的な演目を楽しむポイントなど、歌舞伎鑑賞を助けてくれる一冊となった『音を聴く 深く観る 歌舞伎音楽事始』。著者の土田牧子さんに同書にかける思いを聞いた。
* * *
歌舞伎の幕開きにはチョンチョン、という柝(き)の音が響く。これから芝居が始まる高揚感を観客にもたらす大事な音は、終幕にも使われる。歌舞伎にとって、こうした音楽は欠かせないものだ。
本書は歌舞伎になくてはならない音楽について、近世演劇・音楽を研究してきた土田牧子さん(47)が歴史や楽器の構造、演目とのかかわりなど、網羅的にまとめた一冊だ。
「多種多様な音楽が歌舞伎には使われています。舞台上で演奏される長唄や竹本(義太夫節)、常磐津節、清元節などの舞踊曲。舞台下手の陰で演奏される黒御簾音楽、上手の床で演奏される竹本の語りも重要な役割を担っています。歌舞伎の発展とともに歌舞伎音楽もまた、豊かな世界をつくりあげてきました。本書は初心者の方にもわかりやすく、同時に芝居好きな方が読んでも楽しめるような要素を入れたいと思いました」
土田さんは小学生の頃から歌舞伎に通い、舞台に親しんできた。自身も長唄三味線を杵屋巳太郎さんに師事している。
「あたりまえですが、習って初めてわかることは多いです。自分で弾くようになってから聴くのでは、理解の深さが違ってきます」
音楽劇は海外にもあるが、歌舞伎ならではの特徴は、どんなところにあるのだろう。





































