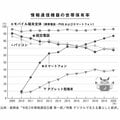スマホが日常のあらゆる場面に侵食し、いつでもどこでも使える状況は、利用時間が伸びる元凶でもあり、目を守る観点からは、感覚が麻痺しているといっても過言ではない状態です。
スマホアイ化のスイッチが入る状況を少しでも減らすために、TPOをわきまえるのも効果的です。スマホを使える時間帯や場所、場面もルールで決めておくのです。

子どもにスマホを持たせた場合は特に、使う場所が問題となってきます。時間帯を区切ったとしても、どこでも使えるとなると、過剰な利用や依存につ ながりかねません。学校への持ち込みが禁止されていないような場合も、できることならば、外での利用は緊急時の連絡や音楽を聞くためなどに限るといった約束をしておきたいところです。
お子さんは嫌がるかもしれませんが、自宅でも、リビングのような親の目が届く範囲でだけ使えるようにするのもいいでしょう。自分の部屋にこもりっきりでスマホを使うとなれば、制限時間は守ったとしても、20分に一度の休憩はおろそかになりそうですし、姿勢がだらけやすい問題もあります。
スマホを使う場所=リビングやダイニングという認識を親子で共有できるようになると安心ですね。
ひと昔前は勉強場所というと子ども部屋がイメージされましたが、近年はいわゆる「リビング学習」がかなり浸透し、リビングやダイニングで勉強している子が7〜8割を占めているようです。
前人未到の偉業を成し遂げた将棋の藤井聡太九段も、中学生棋士としてプロデビューしたころにリビングで勉強や将棋の研究をしていることが話題になりました。
リビング学習は、親に見られていることがプラスに働くともいいます。スマホもリビングで使うものというルールを定めておけば、親にとっては安心感も高まりますし、子どもにとっても、いろいろな面で間違った使い方を防げる効果もあります。