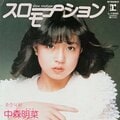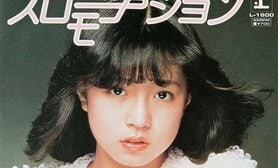「撮影した80人のうち、11歳から18歳までの子どもたちは、はじめはなかなか目を合わせてくれなかったですね。でも通うことで変わりました。人は言葉が通じなくても相手が自分に好意を持っているかどうか感じられる。そうしてだんだん仲良くなって信頼が生まれたりするんです。少し自閉症の特性があったり、恥ずかしくて目をそらしていた子がだんだんコミュニケーションをとるようになってきて、最後はずっと見つめてくれるようになったり」(金さん)
金さんは目と目を合わせ、その人を映像に収める。「自分と異なる背景を持つ人々」の個性と向き合うことを考察する。
「メディアからの取材の多くは校長先生だけに注目し、話を聞いて見学にくる。そうして関係性が生まれないまま帰っていきます。私はどうしても子ども全員と先生たちに出てほしくて、1人ずつ撮り、インタビューをしています」(同)
効率重視と正反対。金さんが大切にする過程はかけた時間や手間で換算されるものとは対極にある。そのすべてが作品で意味をなしている。

映像と写真を行き来
金さんは大阪で育った。大学の被服科を卒業、その後夜間に写真専門学校で学び、まずストレートな写真表現に出合う。
「子どもの頃は絵を少しやっていました。色と光が好きだったので、関連する仕事を探すと、ガラスか写真かと。もともとは手に職をつけようとしたんですね。当初はついていくのに必死。自分だけ『露出って何?』みたいな状態から入りましたし。だから逆に、他の人が撮れないものを、と思っていました」
初個展は公募を経ての写真作品だった。その後、韓国に留学。大学院の写真映像コースに学び、現代アートの文脈から自分の表現へ。映像と写真を行き来する創意の確信は、写真を学び始めた当初からずっとあったという。
「大学院の先生に、君の言いたいことは小説に書くか、映画に撮った方がいい。写真じゃ無理だって言われました。確かに私は言いたいことが多方面にありますし、写真という媒体は自分にはとても抽象的で、本当に難しいと思います」