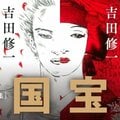大久保被告は当初、女性は朝になって自然死として処理されるだろうと計算していたようだが、呼吸がすぐに止まってしまったために事件となった。
「仮に大久保被告の読み通りになっていたら、次の嘱託殺人が行われていたかもしれません。障害者や高齢者に対するゆがんだ考えを持った人が医療知識を悪用・濫用した事件から、医療者による嘱託殺人や安楽死の是非が議論されることは、間違っています」(児玉さん)
安楽死や自殺ほう助、終末期医療など命に関するテーマを研究対象としている上智大学外国語学部ドイツ語学科の浅見昇吾教授(生命倫理)は「有罪は当然のこと」とした上で今回の判決は「ドイツとの違いが際立っていて興味深い」と指摘する。
ドイツでは、1871年に統一国家が成立して以来、自殺ほう助が認められていると考えられてきた。15年、自殺ほう助団体の宣伝活動や度重なるほう助を防ぐ法律が制定されたが、20年に連邦憲法裁判所がその制限を違憲とする判決を下している。
「憲法に規定されている『人格権』が生きることと同様に、自らの命を絶つことも権利として保障するとしました。また、自分の責任で自由に判断することを認め、自己決定権を尊重する姿勢がはっきりとあらわれた判決でした」(浅見教授)
一方、5日の京都地裁では、大久保被告の弁護側は個人の尊重を定めた憲法13条に照らし、「自分の生き方を決められるということは、生き方の最期も決められるはずだ」とも主張していた。だが判決は、同条は「個人が生存していることが前提であると解釈できる」と指摘。「自らの命を絶つために他者の援助を求める権利は導き出されない」とした。つまり、医療によって殺してもらう権利は認められないということなのだ。
イメージだけの議論よりも、社会保障を見直すべき
全てを自己責任で自由に判断できるとしたドイツに対し、他者の手を借りて死を選ぶことを否定した日本。それぞれの司法が示した価値観の軸足は大きく違う。日本で安楽死を合法化するためには、憲法を改正しなければならず、その実現はそう簡単なことではない。「安楽死を認めよ」という主張が本質をとらえていない理由は、ここにある。