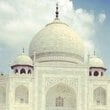なぜ、イスラエル寄りに立つのか。それは、当初からイスラエル支持を表明している米国を意識してのことだとみられます。また、日本として、イスラエルをビジネスパートナーとして非常に重視しているからでもあるでしょう。IT分野などにおいて、イスラエルのスタートアップ企業は多くの独自の技術を持っています。日本企業の活力復活に役立つ可能性を秘めた国として注目が高まっているのです。
ただ、ハマスが襲撃を実行した背景には、イスラエルによるパレスチナ自治区ガザと西岸地域での理不尽で違法な行動があり、そこを解決しなければ、抜本的で恒久的な解決には至りません。これはアラブ諸国はもちろん、国際社会全体が支持している考え方で、米国のバイデン大統領も「二国家解決」こそが重要だと度々言及しています。
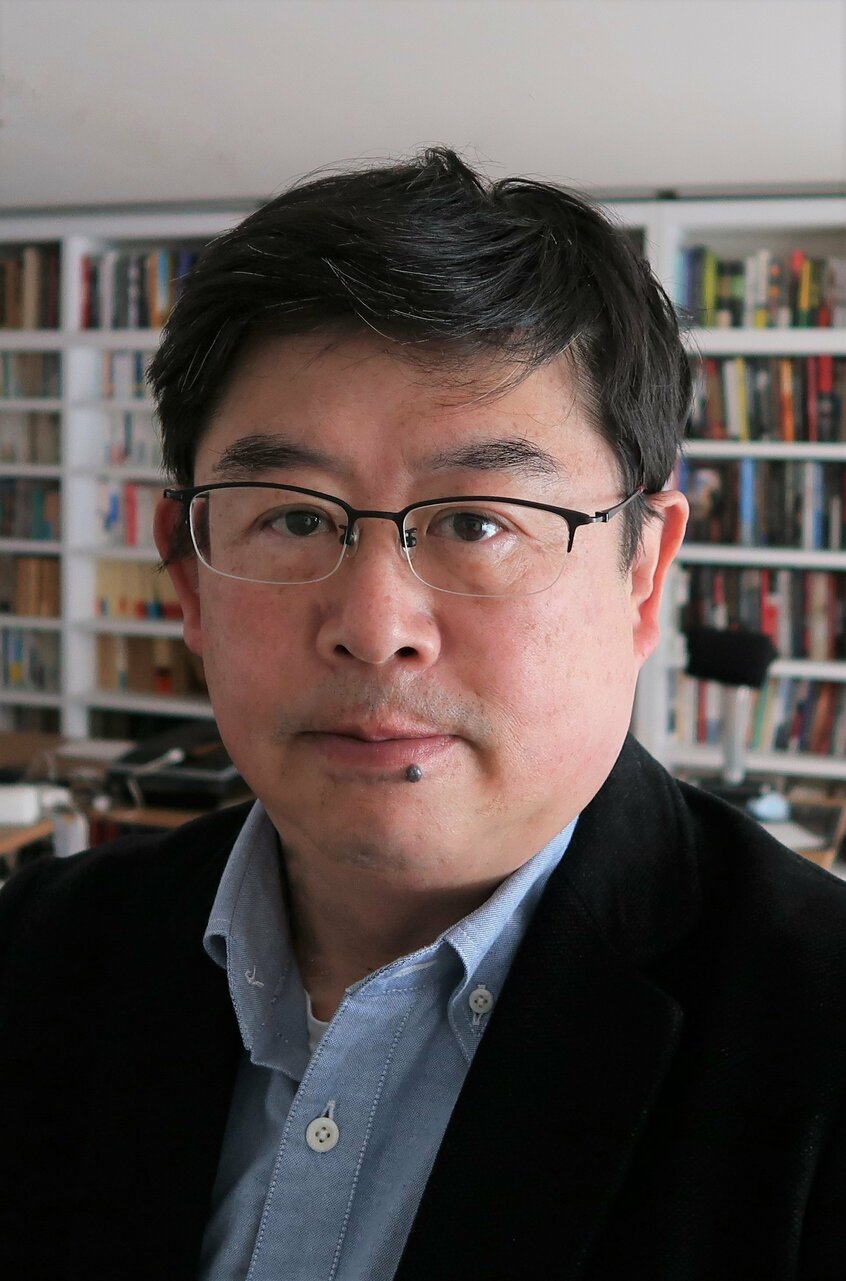
「二国家解決」に触れず
日本も同じ主張をしてきたはずですが、7日以降に出た日本政府の声明の中では、「二国家解決」についてはほとんど触れられていません。二国家解決が重要であること、そしてイスラエルの西岸での入植をやめさせるとする文言も、政府の声明や政府関係者の発言には盛り込む必要があるのではないでしょうか。
犠牲者がさらに増え、アラブ諸国でパレスチナに対する同情心とイスラエルに対する嫌悪感が高まると、それがスピンアウトしてイスラエル支持国に波及する可能性があります。せっかく50年前にアラブ諸国との関係を重視する方針を掲げ、エネルギー分野で密に連携を取り、関係構築をしてきたわけです。日本は長年、パレスチナに大きな経済援助もしてきました。アラブ諸国との温度差が大きくなりすぎる前に、これまでに築いた信頼関係を重視する視点も必要だと考えています。
(構成/編集部・古田真梨子)
※AERA 2023年10月30日号
こちらの記事もおすすめ イスラエル軍の地上侵攻は「不可避」 最悪のシナリオ招くかはイランとロシアの動き次第 慶応大教授が今後の展開を解説