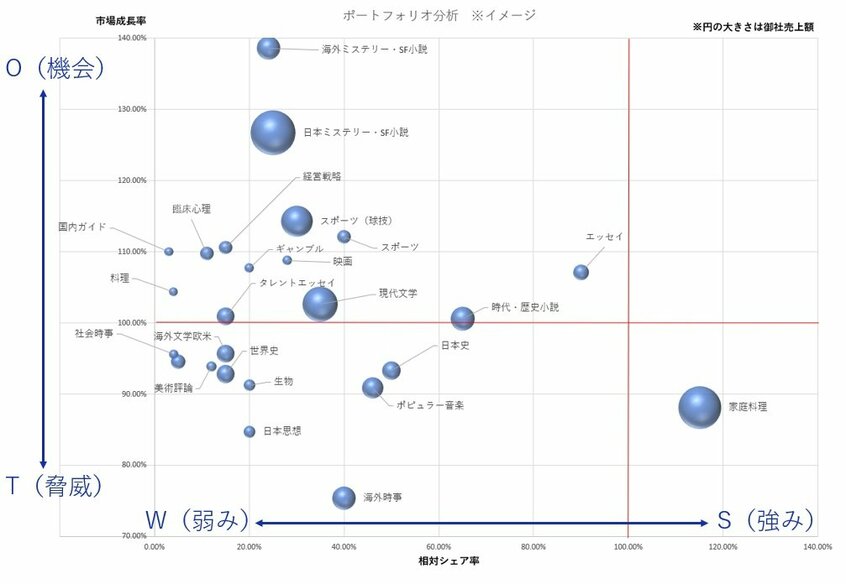
他の業種と違う、出版社の仕組みと課題
出版社は、本や雑誌を作って売ることで経営が成り立っている。しかし、作って売ることに目を向けた場合、他の業種とは違う仕組みが見えてくる。まず、自社で製造の体制を持っていない。また、販売先(本屋やネット書店など)を持っていない出版社が多い。要は出版とは、究極のBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)で成り立っているのだ。編集や販売、販促、などといった必要なところだけに自分たちの機能を強化し、それ以外のところは専門業者に外部委託をしている。また、再販売価格維持で、紙の本の場合どこの書店で購入しても同じ値段で手に入るが、一部例外はあるものの値段を下げて売ることはできない。
以前から、出版業界は多くの構造的な課題を抱え続けているといわれている。その1つが返品率の問題だ。返品率とは書店が仕入れた商品が売れずに、販売会社(取次)に返品される割合のことを言い、現在、書籍は35%超、雑誌は40%超。この高い返品率を改善することが出版業界の大きな課題だ(出版科学研究所 出版関連用語集より)。
編集部との会議により、読まれる本を生み出していく
出版イノベーション事業部では現在、マーケティング分析力を生かしていくつかの出版社と企画や営業の会議を頻繁に開催している。例えば「旅行ガイドブックを出版したいが、北海道や京都といったメジャーな観光地ではなく、今まで取り上げられなかった県やエリアで人気がある場所を知りたい」「子ども向けの学習マンガとして、歴史上の人物でも女性が主役の企画を考えているが、人気なのは誰か?」という編集者からの質問に対して、マーケティング分析から答えを導きだしているのだ。





































