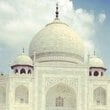生成AIの台頭で大学は変わる。ならば受験勉強にも変化の波は押し寄せる。ChatGPT(チャットGPT)で作られた試験問題に、ChatGPTで勉強に励んだ学生が挑む時代がやってきそうだ。AERA 2023年7月10日号の記事を紹介する。
* * *
たずねたことに、生身の人間顔負けの返事をしてくれる生成AIのChatGPT。昨年11月に発表されてからわずか2カ月で利用者数が全世界で1億人を突破し、各業界に革命を起こさんばかりの勢いで広がっている。それは教育分野も例外ではない。日本の大学にも変化の波が押し寄せ、ChatGPTとの向き合い方をめぐって侃々諤々(かんかんがくがく)の議論が交わされている。
大学が変わる。ということは、大学受験も変わるのだろうか。
「作問能力の低い大学がChatGPTを使って入試問題を作成するケースは増えるでしょう。その結果、それまでの傾向とは違った良問ができる可能性はあります」
と話すのは、大学通信情報調査・編集部部長の井沢秀さんだ。ChatGPTが作成した問題の正誤チェックは当然欠かせないが、問題作成者の負担減にも大きく貢献するとみられる。それは裏を返せば、受験者側は、過去問ばかりにこだわらず、より幅広い対策に取り組まねばならない可能性が出てくるということだ。
大手予備校講師で、『早慶MARCHに入れる中学・高校』(朝日新書)の共著などがある武川晋也さんは、
「ChatGPTによって学力低下が懸念されていますが、本当に進学したい生徒は安易な使い方をしないはずです。それよりも、自分の弱点にフィットした問題をたくさん作ってもらうなど、自分自身で学習を深めるツールとして活用できるのではないでしょうか。受験業界においてChatGPTは、科目によっては最終的には問題集の代わりになっていくのかなと感じています」
と予測する。
■興味を多角的に広げる
受験はもちろん、その先の学びを見据えた時にも、ChatGPTによって自分に合った学習をすることは「非常に有意義」と強調するのは、AIを用いたプロダクト開発会社「LifePrompt」取締役でエンジニアの遠藤聡志さん(24)だ。
「自分の興味を多角的に広げるためにChatGPTはかなり使えると思います」
と話す。兵庫県内の私立高校から現役で東大理Iに進学し、ハードウェアを研究。現在は大学院に在籍中だ。幼い頃から図鑑が大好きで、受験の時期には5センチほどの厚さのある参考書『化学の新研究』を「化学の全てが書いてある」と感動しながら読みふけったという。