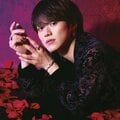一方、市民らの声を受けて、公園再開発の計画が変更になった例もある。
茨城では、県営洞峰公園に民間事業者がクラフトビール工房やグランピング施設、駐車場を建設する計画だった。だが、「静かな環境を変えてほしくない」「樹木伐採が懸念される」という市民の声を受けて、県は今年、地元のつくば市に公園を無償で譲渡する事態になった。
静岡市の城北公園では、コーヒーチェーン店が出店し、駐車場ができる予定だったが、樹木伐採が景観を破壊するとの市民の訴えを受け、コーヒーチェーン店は出店を辞退した。市民は再開発をめぐって市を提訴した。
■「よい公園」とは
ただし、公園の再開発は今に始まったことではない。
遡れば、明治時代にできた東京・上野公園では、動物園が拡張され、美術館ができ、現在の形になった。
前出の大方特任教授は言う。
「公園を作って数十年経てば、施設が老朽化したり、利用者のニーズも変わったりするので、時代に合わせたリニューアルが必要です。大切なことは、新たなデザインが市民の願いに合っているかどうかだと思います」
公園を使う「市民」とは誰を指すのか。
大阪城公園の再開発を追っている大阪公立大学の渡辺拓也研究員は、昨年、再開発前の難波宮跡公園で、利用者に聞き取り調査をした。
「子どもがお金を使わずに楽しめる、このままの自然の公園がいい」と言った女性もいれば、「気兼ねなく来られる」と言った、居場所のない男性もいた。
「再開発後の公園は、きれいになって使いやすくなった人もいるでしょうが、お金がない人、社会に居場所がない人にとっては、使いにくい場所になりました。お金を使うことのできる、稼ぐ市民は行政にとって『よい市民』かもしれませんが、『よい市民』が心地よいと感じる公園が、『すべての市民』にとって『よい公園』とは限りません」
3月に亡くなった音楽家の坂本龍一さんも、同じことを語っていた。坂本さんは亡くなる1カ月前、神宮外苑の樹木について、小池百合子都知事らへの手紙にこうつづった。
「率直に言って、目の前の経済的利益のために先人が100年をかけて守り育ててきた貴重な神宮の樹々を犠牲にすべきではありません。これらの樹々はどんな人にも恩恵をもたらしますが、開発によって恩恵を得るのは一握りの富裕層にしか過ぎません。この樹々は一度失ったら二度と取り戻すことができない自然です」
(編集部・井上有紀子)
※AERA 2023年6月12日号
※当初の記事で、葛西臨海水族園について、「樹木約1400本を伐採することが今年、都議会で明らかになった」とあったのは誤りだったため、「移植の可能性がある樹木が約1400本あるともいわれる」に訂正しました。