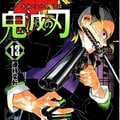2015年1月28日に、中山康樹さんが亡くなった。62歳、悪性リンパ腫だった。
わたしはそのことを、告別式の済んだ2月6日に知った。
わたしは1月28日、中山さんの盟友、カメラマンの内山繁さんのお店Jazz & Cafe “Whisper”にいた。
わたしが企画・編集をし、コラムも連載している【Music Street】の「音楽の聴ける店に行こう!」の取材のためだ。
同行していたオーディオ・ショップ「SOUNDCREATE Legato」の店長、竹田響子さんに、取材前、「内山繁さんのことを知るいい本はないですか?」と質問され、「それなら、中山康樹著の『スイングジャーナル青春録』大阪編と東京編の2冊だろう」と勧めていた。
その本の話をしながら、中山さんとはじめて出会った日のことを思いだしていた。
それは、不思議な出会いだった。
2006年の年末のことだった。
わたしは2003年に20年間勤めたぴあ株式会社を辞め、自分の会社を起業したのだが、当初、予定していた仕事が頓挫し、3年間ほど、定期的に続く仕事もなく、携帯電話とスケジュール帳をもって、釣りなどしながら、日々を過ごしていた。
とうぜん、資金も不安になり始めたので、飲み代の足しにでもしようと、CDや蔵書をネットで販売することにした。もともと、古本屋や中古CD、レコード店の経営にも興味を持っていたので、それはそれなりに楽しい仕事だった。特に、CDはリマスターなどといって、最初に販売したCDよりも音がいいものだといって再発売したり、オリジナル・アルバムに未発表の曲などを加えた+αを売り物にしたもの、同時期のセッションを録音順に並べ直したコンプリートものなどが、盛んに発売されるようになっていた。
そのため、同じCDを何枚か持っているものがあって、まず、そういうものから売っていくことにした。
その中の1枚が、マイルス・デイヴィスの『カインド・オブ・ブルー』だった。
わたしは、その『カインド・オブ・ブルー』を3枚持っていた。1枚は、1983年頃、もっとも初期に発売された最初のCD、オリジナルのレコードと同じ曲数のものだ。次が《フラメンコ・スケッチ》の別テイクが1曲多くはいったもの、そして、もう1枚は、1996年に発売された紙ジャケの『カインド・オブ・ブルー』だった。
紙ジャケのCDも、オリジナル・アルバム+1と1曲多くはいっているので、オリジナルと同じ曲数のCDを販売することにした。リマスターされ、紙ジャケで、しかも、1曲多くはいっているものを持っていれば、それでよいと思ったのだ。
そのCDはすぐに売れた。そして、買ってくれた方の名前を見ると、中山康樹と書かれてあった。あとで知ったのだが、中山さんは+αのおまけの曲を、アルバムの完成度を壊すものだとという考え方を持っていた。また、このCDは、海外の『カインド・オブ・ブルー』のコレクターのために購入したのだとも聞いた。
わたしは、メールを出すことにした。
「失礼ですが、音楽評論家の、あの中山康樹さんですか?」
返事は、すぐに戻ってきた。
「はずかしながら、あの中山康樹です」
わたしにはこういうときに、これもご縁だな、と考えてしまう傾向があって、中山さんに提案をしてみた。
そのころ新しい仕事として、築地本願寺の中にあるブディストホールの運営を任され、もう一つの課題として、自主公演を実施して、ホールの稼働率を上げてほしいというのがあった。
そこでわたしは、中山さんに「ブディストホールで、『マイルスを聴け!』のライヴ版をやりませんか」と提案したのだ。
中山さんは、すぐに返事をくれた。「一度、会いましょう」と。
そして、築地のブディストホールの事務所まで、足を運んでくれたのだった。
まずは、ホールを見ていただき、次に、これまでのわたしの経歴やこれからやりたいことなどの話をした。
話を聞いたあとに、中山さんは、こう言った。
「このホールのキャパは、何人ですか?」
わたしが、164人だと答えると、
「このホールを埋めるのは、わたしには、無理です。小熊さんは、ネット・ビジネスをやりたいんですよね?」
わたしは、これからやりたいことの中で、インターネットを活用したビジネスの話をしていた。
中山さんは、こう続けた。
「インターネットって、ただで読めてしまうじゃないですか、あれ、いやなんです。わたしは、読者にお金を払って、読んでもらいたいんです。もちろん、その価値のある文章を書くつもりです。有料で、読んでもらうサイトを作れますか?」
わたしは、やってみましょう、といった。そして、数日後、見本のページを作って、中山さんに送った。中山さんは、
「いいですね。でも、せっかく書いても、少数の読者しか読んでくれないと、書いていて、空しくなってしまうから、広告を探してみましょう。月に10万もあれば、なんとかなるでしょう。」
わたしは、それもそうだな、と納得し、広告主を探すことにした。
そんなおり、前職で先輩だった人が、築地の会社に就職が決まったので、飲み会をやろうと誘いがかかった。
出かけていくと、その人は、広告代理店の役員になったというのだ。わたしは、まさにこれもご縁と思い、中山康樹さんとの出会いから、有料音楽サイトの計画を話した。そして「広告、紹介してくださいよ」というと、その先輩は「インターネットで広告が取れるわけないじゃないか、無理無理」と相手にもしてもらえなかった。当時はインターネットがビジネスになるとわたしが言っても、周囲の人の多くが笑っていた時代だった。
そんな話を聞いていた朝日新聞社のKさんが、「その企画、うちでやりませんか?」と言ったのだった。「有料で会員だけが読めるサイトなんです。制作費なら少ないですけど出しますよ」
それがはじまりで、朝日新聞社の有料サイト内のコンテンツの一つとして『ジャズ・ストリート』がはじまったのだ。
中山さんと出会って1カ月くらいのうちに企画が決まり、執筆者の候補を決め、依頼交渉をし、2007年4月3日に開始したのだった。中山さんには、『マイルスを聴け!』の連載をお願いした。
そして、この企画は形を変え、無料で読めるサイトとして、2015年の今も、朝日新聞出版のdot.の中で、この【ミュージック・ストリート】として、継続している。
みなさんの多くが中山さんをやさしい人だと話すが、わたしにとっては、とても、とても、怖い人だった。
それまでわたしは、グルメ・ライターや雑誌の取材などの文章を書いてはいたが、編集の責任者になったことはなかった。だから、ツメが甘かったのだと思う。また、中山さんにも、サイト特有の条件がわからないところがあり、どうしてこんなところで行が変わるのだ、などと叱られたこともあった。パソコンの設定などで、行がどこで変わるか決められないのです、などと説明した。
それでも8年、続いているのだ。
そして、なによりうれしかったのが、【ミュージック・ストリート】が開始する時、わたしにもコラムを書いてみたら、と勧めてくれたことだった。6年目のことだ。
そして、わたしのコラムの「第7回 ロボットの次は、3Dですか、クラフトワークさん!?」を書いた後に、中山さんから、メールをいただいた。
「『悪魔のはらわた』、ぼくも公開時に大阪で観ました。本来は大笑いするべき映画なのでしょうが、気持ち悪くて気持ち悪くて。当時を思い出しました。小熊さんは文章力があるのだから、この調子でどんどん書くべきです。それではまた。」
わたしは、天にも昇るようにうれしかった。あの中山康樹にほめられたのだ。
中山さん、わたしが今でもがんばって書き続けていられるのは、このときの、この言葉があるからなんです。
中山さん、ほんとうに、ありがとうございました。中山康樹さんと出会えたご縁に、深く感謝しています。(2015年2月20日)
(小熊一実/プロデューサー)