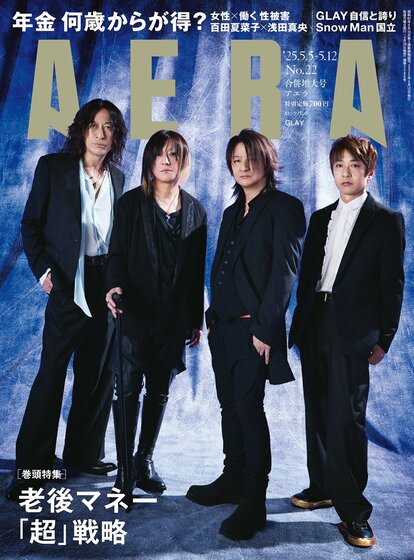〈これほど多くの人、村、町、そして国が、しばしばただひとりの圧政者を耐え忍ぶなどということがありうるのはどのようなわけか〉
そうだよな、人々が自ら進んで権力者に隷従(れいじゅう)するのはなぜなのか。
〈その者が人々を害することができるのは、みながそれを好んで耐え忍んでいるからにほかならない〉
文庫オリジナルで11月に発売されたエティエンヌ・ド・ラ・ボエシ『自発的隷従論』(西谷修監修・山上浩嗣訳)の一節である。それにしても、この言葉、そしてこの書名! ブラック企業に勤める社員。とんでもない政治家に投票しちゃう選挙民。まるで現在の日本社会の話のようだ。
ところがこれは16世紀、日本でいえば戦国時代の書なのである。ラ・ボエシは1530年生まれ。フランスの宮廷に勤める役人で、32歳の若さで没した。この論文を書いたのは16歳か18歳のとき。モンテーニュの親友だったことで辛うじて名前が知られているだけであり、ラ・ボエシ自身は民衆蜂起を煽ったわけでも何でもなかった。だけど、どうでしょ、この言いぐさ。
〈自由を得るためにはただそれを欲しさえすればよいのに、その意志があるだけでよいのに、世のなかには、それでもなお高くつきすぎると考える国民が存在するとは!〉
フランス革命の時代に脚光を浴びたのも納得がゆく。無垢なる人間観察の文章は、だからこそ後世の人々に多大なインスピレーションを与えた。本書の付録の論文でシモーヌ・ヴェイユはスターリニズムと重ねてこれを読み、監修と解説を担当した西谷修はここに今日の不平等な日米関係を見る。たとえば、ほら、こことか。〈人はまず最初に、力によって強制されたり、うち負かされたりして隷従する。だが、のちに現れる人々は、悔いもなく隷従するし、先人たちが強制されてなしたことを、進んで行うようになる〉
〈自発的隷従の第一の原因は、習慣である〉。460年も前の10代の言葉にいちいちグサッとくるって何?
※週刊朝日 2014年1月24日号