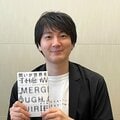■自らの言葉に責任を持つということ
昔から、「吐いた唾は飲めぬ」ということわざがある。一度口から出した言葉はもう取り消せない(だから、注意してしゃべるように)という意味だ。
しかし、ときに政治家などは、「吐いた唾を飲みます」という意味で、「発言を撤回します」と言い放っている。それこそ、『鏡の国のアリス』においてハンプティ・ダンプティが、「反論の余地なくものの見事にやられてしまった」という意味で「まばゆい」と言い放ったように(脇明子訳、岩波少年文庫、2000年、150-151頁)。
ハンプティ・ダンプティの「まばゆい」も、政治家の「発言を撤回します」も、ナンセンスなせりふのはずだ。けれども、自分の言葉に責任を負わず、うやむやにして切り抜けるためには、むしろそうした言葉もどきの方こそが好都合なのだ。
もしも、自分の発言がたとえば事実の誤認に基づいていたのであれば、そのままそう言えばよいだけの話だ。「かくかくという私の認識は誤りでした。しかじかの通り訂正します」と認めることが、人が当然すべき「声振り」である。
しかし、「発言を撤回します」という言葉が「口に出した言葉を取り消す」という意味で用いられ、そのゆがんだ言葉を私たちが拒絶せずに受け入れてしまうのであれば、人は自分の言葉が意味していたはずの認識、考え、構想といったものの誤りを認めなくてよいことになる。自分が何を言ったかに向き合い、それに対して相応の責任を負う必要がなくなる。「言い方が悪かった」という風に当該の言葉遣いだけを訂正して、後は適当に言葉を濁せば済んでしまう。
そしてそうなれば、相手の言葉を真面目に受け取って、それに応答するという、対話の基礎が壊れてしまうことになる。
これが『鏡の国のアリス』のなかの話であれば別にいい。本を閉じればその世界は消えてなくなる。問題は、いま私たちはナンセンス文学をたのしんでいるのではなく、自分たちが暮らしている現実の社会で、この種の状況にたびたび直面しているということだ。しかも、それは往々にして、言葉が最も重視されるべき場で起こっている状況なのである。
◆ふるた・てつや 1979年生まれ。東京大学准教授(倫理学)。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了。著書に『言葉の魂の哲学』(サントリー学芸賞受賞)、『このゲームにはゴールがない』など。