

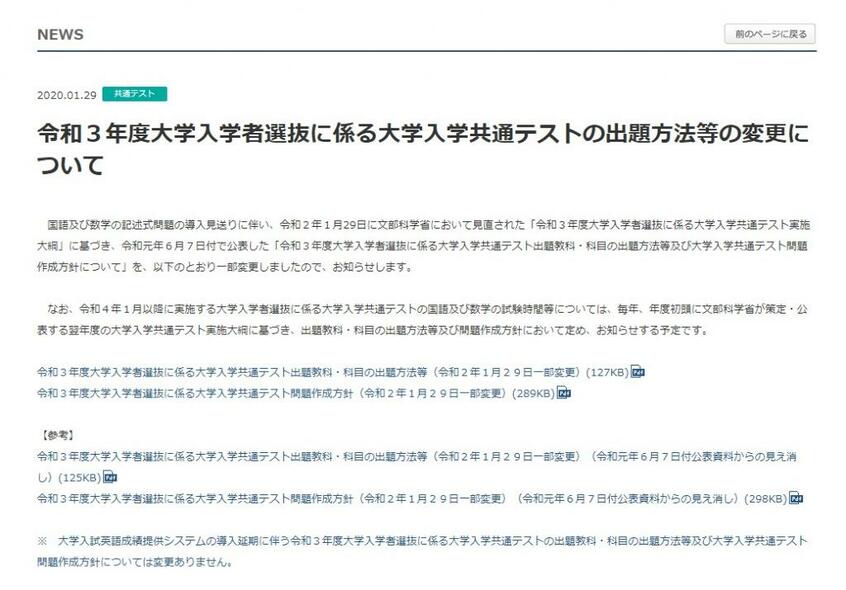
1月29日、「国語・数学記述式問題」見送り後の出題方針がようやく発表された。昨年12月、「英語民間試験」に続き、導入が見送られてから1カ月以上が経つ。国語、数学とも記述式部分を抜き、プレテストで提示した出題方針を踏襲する。2本柱が土壇場で見送られるという、共通テストの失敗の原因は何だったのか。3本目の柱といわれる「主体性評価」にも疑問の声が上がる。AERA2020年2月3日号で、東京大学名誉教授の南風原朝和さん(テスト理論)、京都工芸繊維大学教授の羽藤由美さん(英語スピーキング)、日本大学教授の紅野謙介さん(国語教育)の3人の専門家が分析する。
* * *
──「国語・数学記述式問題」の導入が見送られたのは、昨年12月17日。本日(1月29日)見送り後の出題方針の発表がありました。
紅野:遅すぎますね。実施まですでに1年を切っていますし、入試で大きな変更がある場合は2年前には発表する「2年前予告ルール」があります。大学にそれを求めておきながら、文科省が自ら破るというのは見識を疑います。
──国語はプレテストで出題された記述式の部分が抜け、大問が4問。80分、200点でセンター試験と同じ形に戻りました。
紅野:いま考えられるなかでは一番良識的なところで着地したと思います。大問をプレテスト同様の五つのまま保持し、そこにさらに実用文が入るなどしたら試験としてのバランスを欠くため大いに懸念していました。
──実用文の活用や複数資料といった出題方針自体に変わりはないようです。
紅野:そうした出題形式を全否定する気はないですが、プレテストで出題された問題の質には疑問を感じました。本番までにもっと洗練させた内容にブラッシュアップさせてほしいです。
1月15日、英語の民間試験と国語・数学の記述式の見送りを受けて、萩生田文科相のもと「大学入試のあり方に関する検討会議」の初会合が開かれた。AERAでは、会議に先立ちこの3氏による、検討にあたって「失敗を繰り返さないための三つの提言」を配信した。
──15日に開かれた検討会議をどう見ますか。
南風原:傍聴した印象としては、私たちが提言した「目的と手段を取り違えず、目標を確認・共有すること」「専門家や現場の声を生かすこと」「失敗の検証」の三つは多くの委員に共有されていると感じました。
羽藤:私は今回の失敗の原因は「入試で教育を変える」という発想にあったと思います。
南風原:検討会議でも多くの委員が指摘していました。
羽藤:先の読めない時代に向けて、知識を一方的に注入し、その蓄積を評価する「プロダクト重視」の指導から、環境を整えて生徒の中に思考力や判断力が育つのを促す「プロセス重視」に転換しようとしている。にもかかわらず、その力を「テストで伸ばそう」という発想が古すぎます。そのミスマッチが失敗の根本原因です。
──プロセス重視の学びとはどのようなものですか?
羽藤:例えばイギリスの高校では「スターリンは偉大なリーダーだった。これについて論ぜよ」というような質問が試験に出ます。こういう質問に答えられる日本の生徒はどれくらいいるでしょうか? 何年に何が起きたという史実を習うだけでは不十分。こういう「正解のない問い」に論理的に答えられるような指導が日頃からなされていなければ、入試だけを変えても望む効果は得られません。





































