
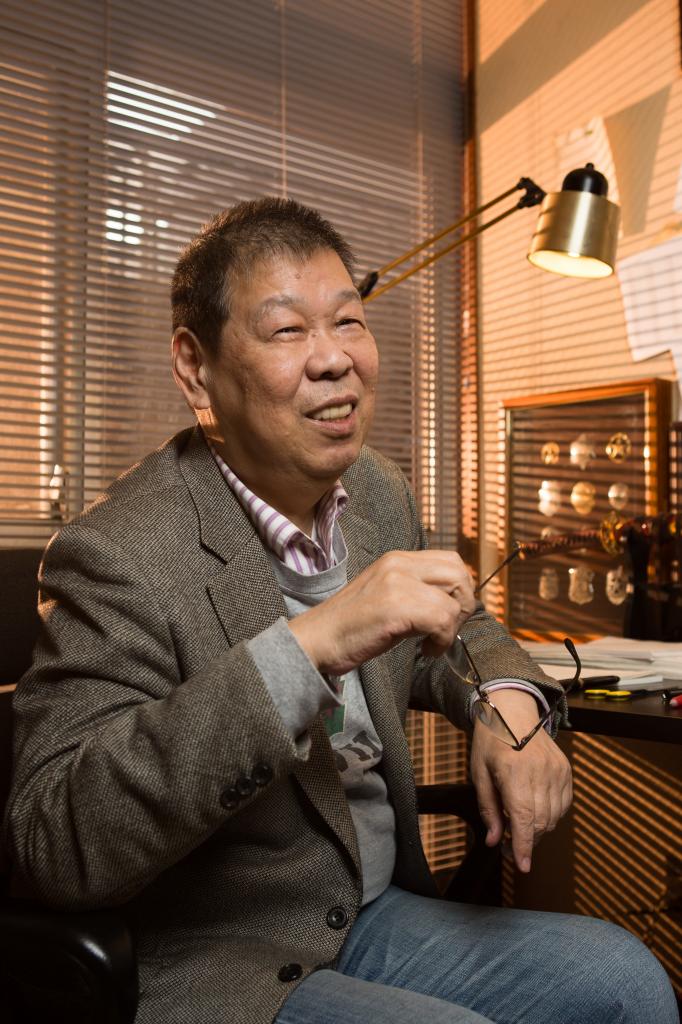
哲学者の内田樹さんの「AERA」巻頭エッセイ「eyes」をお届けします。時事問題に、倫理的視点からアプローチします。
* * *
橋本治さんの葬儀からの帰り道に、女流義太夫の鶴澤寛也さん、『橋本治の小説作法』を制作中の矢内裕子さん、新潮社の足立真穂さんの3人と一献傾けながら、それぞれ「私の橋本治」について少しずつ語った。
そのときに寛也さんが「橋本さんは千手観音のような人だった」とぽつりと言った。千手観音は衆生をあまねく済度するために千の手を持っている。橋本さんは支援を求める人がいると「うう、めんどくせえなァ」とぶつぶつ言いながらでも、必ず手を差し伸べた。聞いてちょっと驚いたのは、僕も前に「橋本治は薬師如来のような人だ」と書いたことがあるからだ。
作家への評言にはいろいろなものがあり得るけれど、仏さまに喩えられる作家はまず橋本さんを措いて他にはいないだろう。
葬儀の2日前、橋本さんの訃報が届いた直後、高橋源一郎さんと大阪の朝日カルチャーセンターで対談した。「平成のおわりに」というタイトルだったけれど、ほとんど「橋本治とはなにものだったのか」という話題に終始した。そのときに高橋さんが「橋本さんは時代をして語らしめることのできた稀有の作家だった」と語った。
その通りだと思った。『巡礼』から『草薙の剣』に至る連作の中で語っていたのは、登場人物たちというよりは、「昭和という時代」そのものだったのだと思う。
時代は自分の言葉を持っていない。まとまりのある命題や審美的判断を時代が語るということはあり得ない。でも、橋本さんはそれを語らせようとした。時代に言葉を贈ろうとした。
そのために、橋本さんが採用したのは「もともと自分を語る言葉を持っていない人たち」を語り手に配することだった。彼らは自分の言葉を持たない。だから定型句や空語を繰り返し、しばしば言いよどみ、口をつぐむ。でも、言葉をうまく操れないこの「こわばった舌」を通じてはじめて時代は語り始める。橋本さんはそれを実践してみせた。例外的な力業だったと思う。
言葉を持たないものに言葉を贈ったこと。その動機として「慈愛」の他に何があるだろうか。橋本治さんが仏さまに喩えられるのはそれゆえだと僕は思う。
※AERA 2019年2月25日号







































