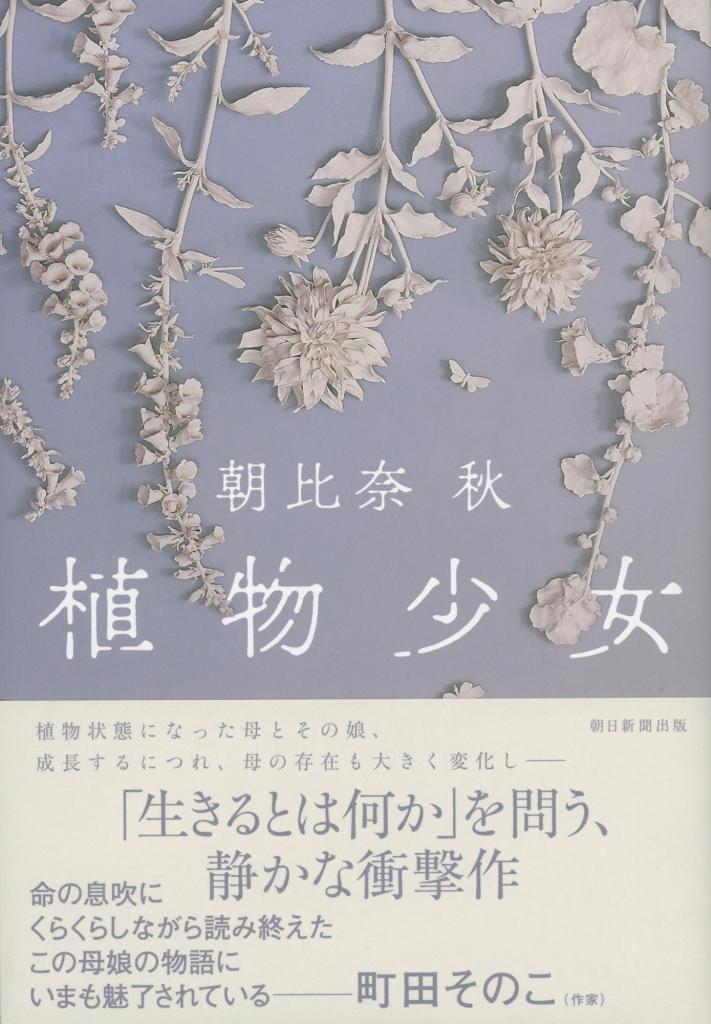
※Amazonで本の詳細を見る
<わたし>は母親のいる病室に通い、そこを居場所として育っていく。物語は四部構成になっており、第一部で描かれるのは<わたし>の幼少期だ。まだ体の小さな彼女は、深雪の太腿を枕にして微睡む。2人の間に会話はないが、<わたし>にとって母親のそばがもっともくつろげる居場所である。深雪と呼吸のリズムが完全に同期したとき、「母がこうなってしまった経緯さえもどうでもよくなって、ただ黙って一緒に呼吸するだけにな」り、“ママの娘やから”“わたしも植物なんかも”と「声帯を使わずに」心の奥で囁くのである。第二部では美桜が成長して高校生になっている。学校の部活で不快な人間関係に巻き込まれた<わたし>は、母親に憤りをぶつけようとする。無言の深雪はすべてを受け止めるからだ。
医療小説としての技巧を尽くして、静止したままの深雪がまぎれもなく生きているということが示される第一層では、呼吸がモチーフとして用いられた。その下の第二層では<わたし>はさまざまな声に取り巻かれる。
学校で中傷に晒されて悩まされるだけではない。植物状態であり続ける深雪のことをさまざまに言う者がいる。たとえそれが同情から来た言葉であっても、<わたし>にとっては自分と母親の間に入ってきてもらいたくないものなのだ。父親と祖母から自分を生んで病に倒れる前の深雪について聞かされると、自分が肌を触れあわせている母親とその像が重ならなくなって<わたし>は動揺する。言葉は否応なく心に入り込み、時にはそれを上書きする。言葉によって失われるものがあることが第二層では示される。
静謐な小説だが、第二部では作品を覆う被膜が破れ、渦巻く感情が露呈する。声に追われた<わたし>は、逃れるように夜道を全力で走り、言葉が不要な呼吸だけの境地を体験する。「息だけをして生きる、この確かな実感の連続」の中に母親がいるのだとすれば、みじめでも空っぽでもないと考えることが救済となるのだ。しかし言葉から完全に解放されることはできない<わたし>は、再び声の渦巻く日常の中へと戻っていく。このように、第二層で『植物少女』は言語の小説という性格を露わにする。





































