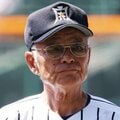約10カ国のアンテナを活用できるネットワークを構築し、衛星事業者などに時間単位で貸し出す。ビッグデータやAIなど衛星データビジネスが活況を呈する中、確実なニーズが見込まれるが、国内外に同業社はほぼ皆無という。CEOの倉原直美(36)はスピード感をもって事業展開に臨む一方、「競合社が増えないといけない」との認識だ。市場を独占することよりも、「衛星データの有効利用で世界を変えたい」思いのほうが強いのだ。倉原の「宇宙人生」をたどろう。
大分県出身の倉原は小学生のころ、宇宙テーマパーク「スペースワールド」(北九州市、昨年閉鎖)に夢見心地で通った。憧れの職業は宇宙飛行士。将来宇宙に行くためのキャリアやスキルを磨きたい。そんな思いから、大学受験は航空宇宙関係の学科に絞った。大学で人工衛星の開発研究者、趙孟佑(ちょうめんう)の薫陶を受け、衛星エンジニアの道を歩み始める。
起業を決意したのは、米国の大手企業やNASAに就職していた同年代の研究者仲間が、相次いで欧米の宇宙ベンチャーに移籍したことに触発されたのが大きい。倉原は言う。
「宇宙業界全体が大きな成長を遂げようとしている時期に、スタートアップとして変化の渦に身を置くワクワク感は圧倒的な魅力です」
20人のスタッフは世界7カ国にまたがり、海外出身者がほぼ半数を占める。社内の公用語は英語だ。そんな社内で、倉原は4月に保育所に預けるまで毎朝、子連れで出勤した。月2週間は海外出張。分刻みのスケジュールをこなす、倉原の疾走は止まりそうにない。
野村総合研究所(NRI)上級コンサルタントの佐藤将史(40)は、宇宙ベンチャー経営者の特質をこう指摘する。
「育った環境や出身大学もキャラクターもばらばらですが、共通項を挙げれば、面白いことにチャレンジしたいという熱い思い。それから、留学や外資系企業勤務の経験などを通じてグローバルな感覚を磨いてきたことではないでしょうか」
佐藤自身、東京大学、同大学院で地球惑星物理学を専攻した宇宙の専門家だ。東日本大震災後、生き方や価値観を見つめ直す体験を経て、米国に留学。現地で「スペースX」に転職した友人に再会したとき「自分だけ取り残されている」と感じ、宇宙ベンチャーを追うようになった。佐藤は言う。
「日本がトップリーダーになれる、ポテンシャルのある分野だと思います」
(文中敬称略)
(編集部・渡辺豪)
※AERA 2018年4月30日-5月7日合併号より抜粋