


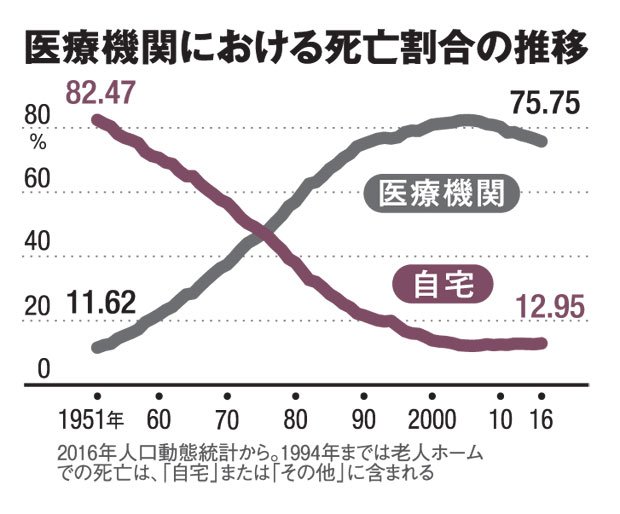
「看取り士は今年10月末時点で300人を超えました。最近は余命告知を受けた親を自宅で看取るために、看取り士資格を取る人も増えています。大病院の裏口ではなく、狭くても自宅玄関から堂々と親を送り出してあげたいと考える人たちです」
一般社団法人日本看取り士会の柴田久美子会長(65)はそう話す。彼女はかつて島根県の離島で、病院ではなく生まれ育った島で死にたいという人たちを集めて看取りの家を運営。島内外で200人近い高齢者をその胸に抱いて看取ってきた。2012年には日本看取り士会を設立。岡山市に本部があり、全国6カ所に研修所がある。
「私たち看取り士は余命告知を受けてから長い場合で3カ月、短いと2週間で、ご本人の状態を見ながら定期的に自宅などを訪問します。時給4千円です。ご本人が死を受け入れて幸せに逝くために、ご家族が幸せに看取るために、作法や考え方をお伝えしていきます」(柴田さん)
近所の医師との連携も行う。自宅死の場合、医師の死亡診断書がなければ、警察が来て事情聴取などが行われるためだ。
看取り士をテーマに9月に出版した拙著『抱きしめて看取る理由』(ワニブックス【PLUS】新書)でも取材した、高原ふさ子さん(58)と長女の由津莉さん(23)にあらためて話を聞いた。高原さんは実母を看取るために看取り士になった一人。
●自宅マンションで介護
高原さんの母の啓子さん(当時83)が脳卒中を発症したのは13年5月。右半身マヒで口もきけず、自力で食べることもできない寝たきりになった。延命治療をしきりに勧めてくれる病院に、高原さんは「死は病気じゃないから延命はしたくない」「母は自宅で看取りたい」と訴え続けた。だが、働きながら自宅で介護するには胃ろうが避けられないと知り、断腸の思いで受け入れた。
都内の自宅マンションで介護生活を始めたのは同年10月。会社員として働きながら、日中はデイサービスなどをフル活用する生活だった。当時、学生だった由津莉さんも、祖母を退院させて介護をすると聞いて自宅に戻った。由津莉さんにとっての祖母は、幼かった自分をおんぶして散歩に連れていってくれた優しいおばあちゃん。
高原さんは、幼かった娘が散歩時に祖母が愛用していたコートを引きずってきて、散歩をせがんでいた光景を覚えている。




































