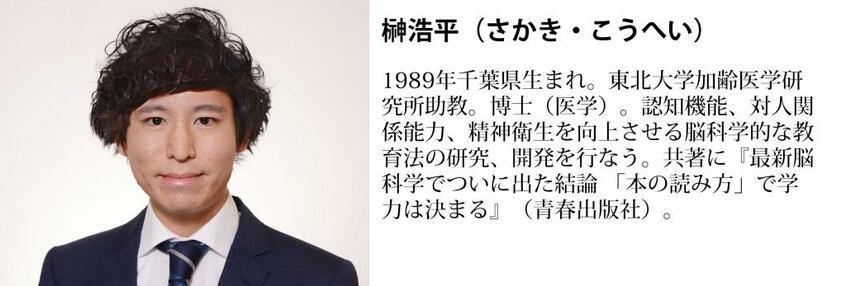課題に取り組んでいる間、学生さんの背後に自分のスマホを置いてもらい、「課題中はスマホを触ってはいけません」という指示をしました。
検査をしない残りの2人には、LINEでグループトークを続けてもらいました。すると、パソコンで集中力を調べる課題に挑戦している学生さんの背後のスマホに通知が届き、音が鳴ります。しかし、検査中のため見ることができません。このようにして、「勉強中にLINEの通知が届いて、気になってしょうがない……!」という状態を実験室の中で再現したのです。
音が鳴って集中力が下がるのは当たり前のことなので、LINEの通知音と同じ頻度でアラームの音を鳴らす条件下でも検査を行ない、集中力の指標を比べました。
解析の結果、アラームの音を鳴らしたときと比べて、LINEの通知が鳴ったときの方がボタンを押すまでの平均時間が長くなりました。さらに、素早く押せたり、気を取られて遅れてしまったりするような、ボタンを押すまでの時間のばらつきが大きくなっていました。これらの結果から、LINEの通知音は集中力を下げていることがわかりました。
さらに、「早く返信しないと嫌われちゃう……!」といった、対人関係に抱く不安の傾向が高い人ほど、通知音によって集中力が下げられる程度が大きいことも明らかになりました。
この実験のポイントは、実際にスマホを操作しているわけではないというところです。「ながら勉強」をしていなかったとしても、勉強中にスマホが机の上にあって、通知が届くだけでも、集中力が下がってしまうということを意味しています。この実験の結果からも、やはり「勉強中はスマホの電源を切ってリビングなどに置き、目に入らないようにする」ということを徹底するべきだといえます。