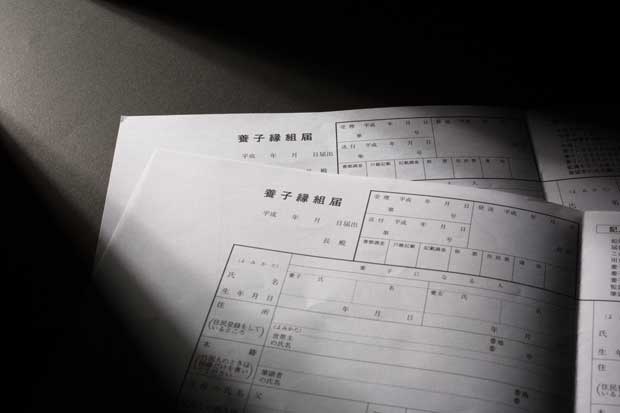



課税対象者が大幅に増えた相続税。流行の節税対策や税理士業界の裏事情、“争続”が起こりやすいケースなど、普段は聞けないことをズバリ聞いてみた。
──2015年の相続税法改正で基礎控除額が引き下げられた(従来の「5千万円+相続人数×1千万円」から「3千万円+相続人数×600万円」に)ことで、課税対象者が大幅に増えたと言われています。相続税申告を行う税理士はさぞかし儲かっているのでは……?
福留:15年に相続税の課税対象となった人は10万人を超え、税制改正前に比べて1.8倍に増えたと言われています。その影響で相続税申告の依頼や相続対策の相談件数が増えたのは事実です。うちの事務所で言うと、昨年の相続税申告件数は706件でしたが、今年は1千件を超えそうな勢い。今、税理士業界では資産税を扱う事務所が急速に伸びており、人材の採用が追いついていない状況です。
高原:ただ、昨年の中ごろまでは相続対策の依頼が引きも切らない状況でした。生前贈与花盛りだったんです。
●「相続税が得意です」
──贈与の相手1人につき年110万円の非課税枠を利用して、子や孫に贈与する人が多かったということですか?
高原:それももちろんありますが、教育資金の一括贈与(受贈者1人につき1500万円まで非課税)や住宅取得等資金贈与(省エネ等住宅ならば最大1200万円まで非課税)の申告件数が増加傾向にあったんです。ところが、昨年6月に消費税10%への引き上げが延期されて、住宅の駆け込み需要が急激に減ってしまい、その影響で住宅取得等資金贈与の件数も減りました。この贈与の非課税枠は年々減っていく予定(21年4月には省エネ等住宅の非課税枠は800万円に減額予定)なので、まだまだ利用される人はいるかなと思っていたのですが、昨年ガクッと減ったきり増えていないように感じます。
寺町:「相続に強い」とアピールする税理士事務所は急激に増えましたよね。年間の相続税申告件数は10万件ほどなので、全国で税理士登録されている7万6千人で割ると、年間で1人あたり1件ちょっとの申告書を作成できる計算になります。しかし実際には相続を得意とする税理士事務所に案件が集中しますので、年間に1件も相続税申告書を作成しない税理士のほうが多数です。ところが、15年の相続税法改正で課税対象者が増えるのがわかった途端、「相続税が得意です」とHPに掲げる税理士事務所が増えました。相続絡みの仕事の取り合いになっている印象を受けます。
高原:その影響か、“相続税還付”の依頼も増えています。





































