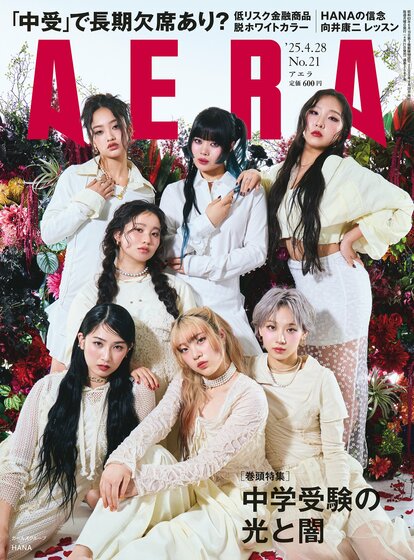谷村は加山雄三と作った「サライ」(92年)において「サクラ吹雪」を高らかに謳いあげたし、さだは山口百恵に書いた「秋桜」(77年)において、わざわざコスモスを和名表記にすることで桜のイメージをそこにしのばせるなどした。こうした戦後生まれのアーティストたちが、敗戦によってともすれば負のイメージがついた桜の「復権」ともいうべき作業を重ねたことで、桜ソング、ひいては「さくら色の卒業ソング」が気軽に愉しめる土壌が耕されていったのである。
そういえば、森山はさだがグレープ時代に作った「掌」をカバーしている。もともと、母・良子の愛唱歌で、彼が幼い頃によく聴かされたという。一昨年には「ミュージックフェア」(フジテレビ系)の2700回記念コンサートで、彼とさだ、谷村が中心になって桜ソングメドレーを披露したりした。
森山の「さくら(独唱)」そして、それ以降に生まれた桜ソングに、軍国主義のイメージを想起する人は皆無に近いだろう。この曲はある世代以上の日本人が長年悩まされた「敗戦コンプレックス」を払拭させ、そこから解放した。まさに、戦後からの「卒業」も体現したという歴史的名曲なのだ。
●宝泉薫(ほうせん・かおる)/1964年生まれ。早稲田大学第一文学部除籍後、ミニコミ誌『よい子の歌謡曲』発行人を経て『週刊明星』『宝島30』『テレビブロス』などに執筆する。著書に『平成の死 追悼は生きる糧』『平成「一発屋」見聞録』『文春ムック あのアイドルがなぜヌードに』など。