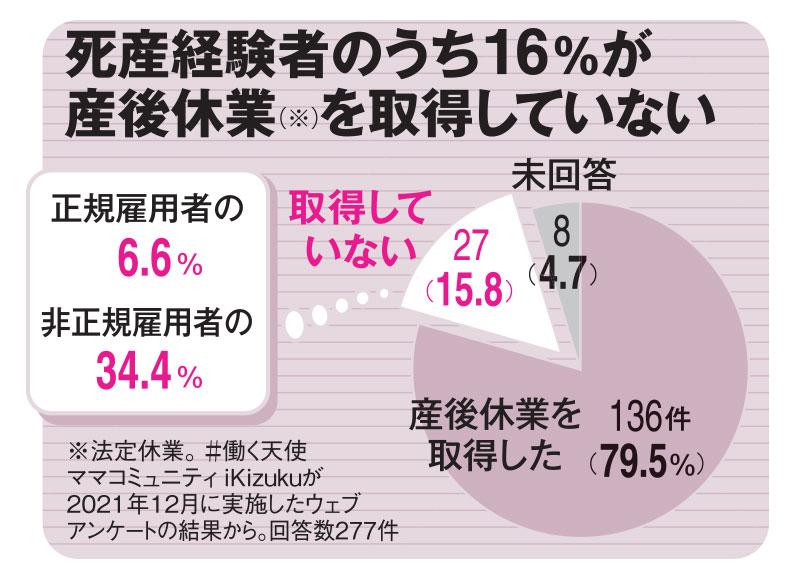
妊娠12週未満の流産の場合は休暇制度などもなく、前出のiKizukuの調査では半数以上が当日や数日の休暇を取得しただけで復帰していた。
流産・死産後1年以内の働く女性は、医師からの指導によって一定期間の休業や勤務配慮などの「母性健康管理措置」を受けられるが、制度が知られておらず、十分に活用されていない。
厚生労働省が昨年公表した調査結果によると、流産や死産で赤ちゃんを亡くした女性の65%が「うつ・不安障害が疑われる」という結果だった。
『大切な人を亡くした人の気持ちがわかる本』の著者で、中央大学人文科学研究所客員研究員の高橋聡美さんはこう話す。
「赤ちゃんが生まれるということは、一般的に多くの人に祝福されるとてもハッピーなできごと。それが死産で一気に奈落の底に落ちるような悲しい経験に変わってしまう。その落差が、お母さんたちの悲しみをさらに深いものにしてしまいます」
■同僚の励ましに傷つく
また、流産や死産後の心身の変化も大きいという。
「『産後うつ』と言われるように、産後はもともとホルモン分泌が変化し、うつになりやすい。さらにおなかの赤ちゃんを失ったグリーフが加わり、うつ病のリスクも高い状態です。母体も産後と同じダメージを受けているので、以前と同じコンディションで働けないことを本人も周囲も理解することが必要です」
おなかの中の赤ちゃんを亡くした場合、親や配偶者、子を亡くす場合とはまた違う苦しみが生まれることがあるという。
その一つが後悔だ。ただでさえ身内などを亡くすと、「すぐに救急車を呼んでおけば……」など後悔がついて回る。流産や死産は、すべてが母体のなかで起こるため、女性が自分の責任と考えがちで、さまざまな後悔に苦しむ、と高橋さんは言う。
また、働く女性の場合は、流産や死産後に産休などの制度を使い、仕事を休む理由を説明するため、上司らに流産や死産を報告せざるを得ない。そこで、上司や同僚から掛けられた言葉で、傷つくケースも少なくない。相手に悪気がない分、受け入れられない自分はダメな人間だと苦しむ負のスパイラルに陥る。
「『まだ若いんだから、またがんばって作ればいい』とか、『障害を持って生まれてくるよりよかったのかも?』といった間違った励ましの言葉に、傷つけられる母親は多い。働く女性が増え、職場に死産や流産を経験した社員がいることは珍しいことではありません。社会全体でグリーフ・リテラシーを上げていくことが必要です」(高橋さん)
(ライター・福光恵/編集部・深澤友紀)
※AERA 2023年2月20日号






































