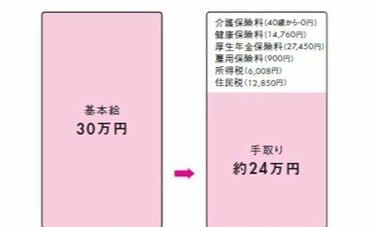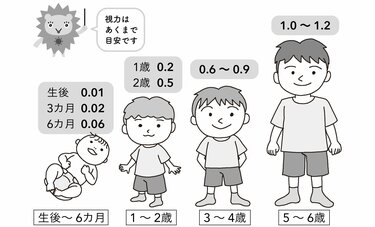実際、インターン参加者を採用するメリットは多くの企業関係者が口にする。フリマアプリ運営で知られるメルカリでは、多くのポジションで採用選考受験にインターン参加を必須としている。メルカリはインターンを含む採用窓口を通年でオープンし、学年にかかわらず応募が可能だ。そして、インターン生にも社員とほぼ同様の情報と役割を与え、社の一員として仕事に取り組んでもらうという。同社新卒採用チームマネージャーの渡辺理香さんは言う。
「3カ月程度の長期で配属先の仕事をしてもらい、給与も支払います。通常の会社説明会や面接を担当しないようなポジションのスタッフともかかわるので表面上ではなく深く会社のことを知ってもらえますし、私たちも通常の選考だけでは知ることができない学生の能力や特性を正しく評価することができる。ウィンウィンのシステムです」
京都大学出身で今年4月に新卒入社したエンジニアの中田健誠さんは、大学3年次の1~3月にインターンし、そのまま本選考に進んで入社を決めた。さらに、入社前の半年間も内定者の立場でインターンしたという。
■採用直結型が解禁
エンジニアのインターンは比較的期間が長く、実際に業務の一端を担うケースが多いが、それでもメルカリのインターンは印象的だったと振り返る。
「インターンには6~7社くらい参加しました。中でもメルカリは与えられる権限や情報が大きくてやりたいタスクに取り組めました。社員も対等に接してくれていい意味でインターンらしくなかった。これらは新卒入社しても同じだろうと思い、本選考に進むことを決めました」
こうした流れを受け、政府主導の就活ルールでも25年卒から採用直結型インターンを解禁する予定だ。5日間以上の日程で、半分以上を就業体験に充てるインターンなどについて、インターン時の情報を採用選考に使用できるようになる。現状は1~3日の日程で実施する企業が多く、「5日以上」のハードルは高い。今のところ様子見という企業が多いが、期待する学生もいる。25年卒にあたる早稲田大学2年の女子学生は言う。
「就活という意味では、それほど大きく変わらないかもしれません。ただ、本来のインターンの意味でもある『就業体験』がしっかりできる機会が増えるのではないかと期待しています」
「就活」の目線だけのインターンに学生生活の時間を割かざるを得ないのは損失だ。しかし、本来的な意味での就業体験ならば貴重な機会にもなるだろう。(編集部・川口穣)
※AERA 2022年10月24日号より抜粋
 川口穣
川口穣