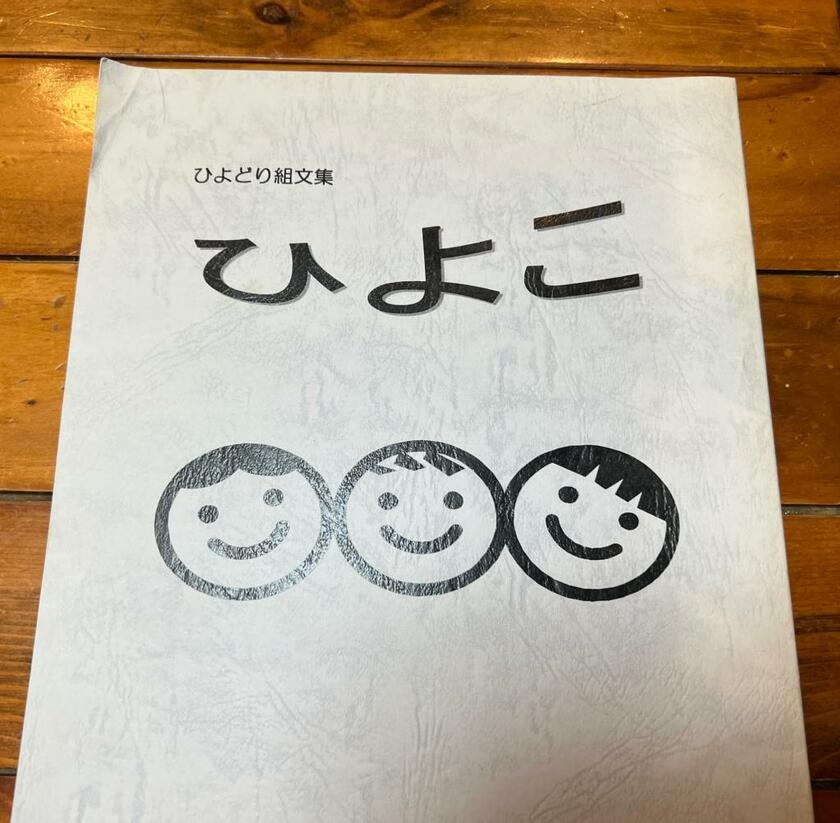
■何を書いてもいいから
「ぴぴちゃん、先生と交換日記しない? 先生もぴぴちゃんくらいの時に、よく学校の先生にお手紙を書いて渡したんだよ。何を書いてもいいから持っておいでよ」
りょうこ先生のクラスでは、日記は毎日の宿題であり、毎回、うれしくなるようなコメントを書いてくださったことを思い出しました。
その後、実際に先生と次女が交換日記をしたのかはわかりません。でも、難しい年齢に差しかかったきょうだい児には、家族以外にも寄り添ってくれる大人が必要なのだと実感しました。
ある時、りょうこ先生に「クラスのどんなにませている子でも、今のぴぴちゃんの気持ちや状況を理解することはできないと思います」と言われたことがありました。だから、周りにいる大人が「大丈夫だよ、ちゃんと見ているよ」と示すことが大切だと思う……と。
■ホッとした表情に
この頃の次女は、常に冷静を装いながらも、先生が関わって下さるたびにホッとした表情を見せるのが印象的でした。
実はこのエピソードは、これまでに何度か、きょうだい支援に関する話題として、講義や学会などでお話ししたことがあります。りょうこ先生と次女のやり取りを聴いた学生さんが、卒論でりょうこ先生にインタビューを依頼したこともありました。
今回、保護者とは少し違う角度で、先生にはどう見えていたのかと聞いたところ、次女のことを書いたファイルを送って下さいました。
ご本人の許可を得て、抜粋して紹介します。
【教師の仕事は教科指導や生活指導など、さまざまある。しかし、どんな仕事でも、中心にいるのは「子ども」である。目の前の子どもをどう見るか、どう理解するかということで、授業づくりを進めたり、日々の問題との向き合い方が変わってくる。私は、子どもをよく見ること、関わること、つながることを通して、子ども理解を深めていこうと思い、日々の教育実践をしている。
今から8年前。高学年が続いて、久しぶりに1年を担任することになった。元気な男の子が多く、入学式からずっとにぎやかなクラスだった。そんな中にぴぴちゃんがいた。クラスの3分の1は幼稚園からの友達であったせいか、いつも仲良しのお友達と一緒にいた。
昼食時間にグループのところで一緒にご飯を食べながら、子どもたちの話を聞くのが私の楽しみの1つである。多くの子どもが「先生!あのね…」と家族のこと、習い事のことなど、話を聞いてもらいたくて自分からどんどん話す。
ぴぴちゃんは、こちらから話しかければ話すが、自分からは話さない。
返事も「うん」「ううん」くらい。自分でたいていのことができるぴぴちゃんだったので、お友達が困っていることは「先生、○○ちゃん困ってるよ」とそばにきて話してくれた。「おとなしいけれど、しっかりしている子だな」と思った。
そのうち、保護者面談を通じて、双子のお姉さんが車いすで生活していること、弟は足が不自由でリハビリをしていることなど、家庭の様子を知ることができた。その時は「お母さん、大変だな」と思うくらいで、それがぴぴちゃんにとってどういう影響を与えているのか?ということまで考えが及ばなかった。
 江利川ちひろ
江利川ちひろ

















