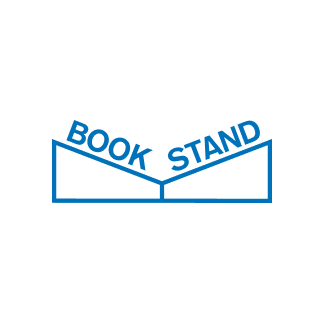夏子が亡くなってからも、彼女について考えることを拒絶していた幸夫ですが、真平たちと共に時間を過ごすうち、次第に夏子という存在と向き合いはじめるようになります。彼女は何を考えていたのだろうか、自分の言動が彼女に何を思わせていたのだろうか。静かに過去を振り返りながら、今までの共に生きていることのできた日々を何故もっと大事にしなかったのか、夏子に、あるいは自分に向けた永い言い訳の日々がはじまります。
「今更だけど、風邪をこじらせたとき、君に言った言葉を後悔してる。病院に行けと口うるさい君に俺は、関係ないだろ、と言ったの、憶えてるだろ。俺がいつ死のうが俺の勝手だと、本気でずっと思っていたんだ。後悔してる。俺はいったい何のために、君と一緒に居たのかね。あのあと君は家を出て、夜半まで町を歩きながら、どんな思いを巡らせたことか。その時だけの話じゃないわよ。と君は言うだろ? そうだろう。すべてがとりとめもなく、終わりそうもない言い訳めいているが、これから俺はきっと、死ぬまでかけて、いくつも君に放った言葉のあれやこれ、取った態度のあれやこれ、を、じわじわと、思い出しながら、背中にいやな汗をかいて、生きて行くんだろう」(本作より)
4人の交流の様子、家族を失ってからの日々の生活、そして妻を、母を失くしたという事実と共に生きていこうと葛藤する......その様子が4人各々の視点から、また彼らを取り巻く人びとの視点から綴られていくことにより、登場人物たちの心の動きがより鮮明に浮かび上がってくる作品となっています。