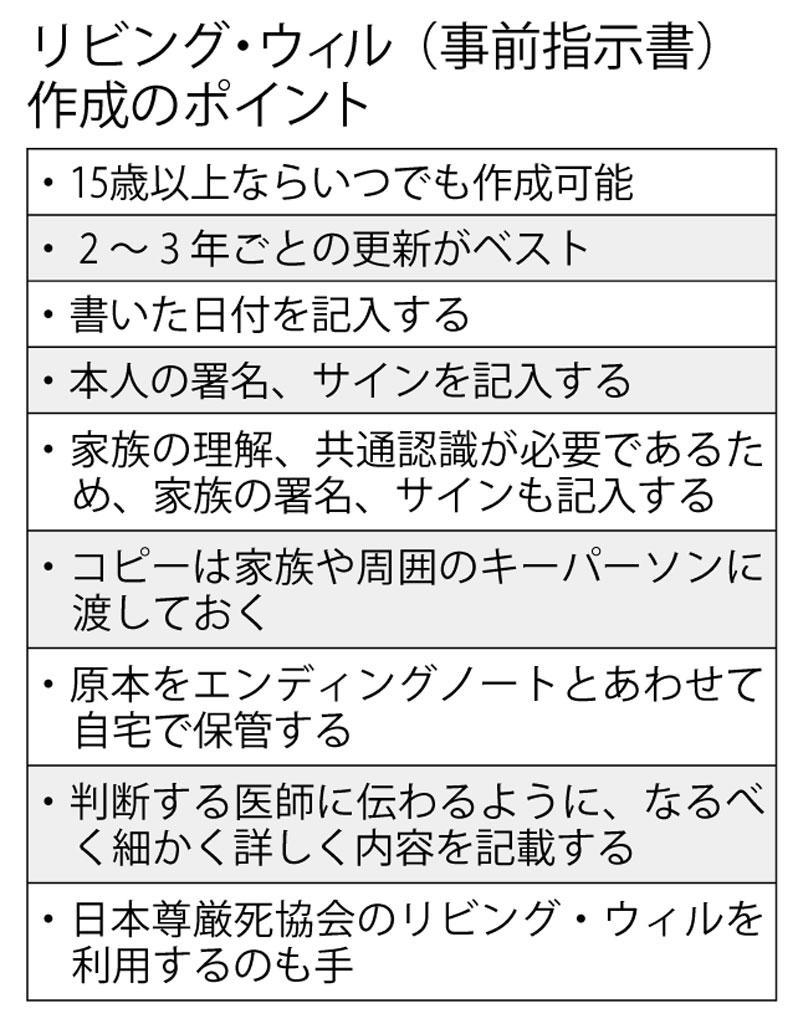
例えば、「食べられなくなっても胃ろうはつけないでください」「死期が迫っていると判断されたら、病院での治療は望みません。延命措置はせず、自宅での最期を望みます」など、自分の意思をなるべく具体的にメモに残す。延命治療を望む場合にも、その旨を記すことが大事だ。特に決まった形式や書式はないが、「延命治療は希望しません」のみでは、判断する医師にも伝わりにくい。何をどこまでしてほしい、あるいはしてほしくないかを明記することが、いざというときの医師や家族の判断材料になりやすい。
一口に延命治療といっても、栄養や水分を補給する手段だけで、胃に穴を開けて栄養分を注入する「胃ろう」なのか、鼻から管を入れる「経鼻胃管」なのか、点滴なのかなど、さまざまなレベルがある。特に胃ろうに対するマイナスのイメージが先行しがちな今、延命治療そのものに対し、誤った認識を持ったまま決断を迫られる例も見られている。
例えば、「母は延命治療をしないと決めていたので、胃ろうはせずに、鼻から管を入れてもらった」というケース。延命治療という点においては、胃ろうも鼻からの管も、方法が違うだけで同じ意味になる。だが「胃ろう=延命治療、鼻から管を入れて人工栄養を送ることは延命治療ではない」という誤解から、望まない治療を始めてしまう例も見られるのだ。年間100人以上の看取りを支える在宅医療専門医の中村明澄医師(向日葵クリニック院長)は言う。
「延命治療は、『とりあえず』で始めることは絶対にお勧めしません。『それを外したら死に至る』というものをつけるかどうか。治療ではなく、延命させるということ自体が、本人や家族にとってどうかということを、しっかりと考えておく必要があります」
だが“命のしまい方”を本人や家族だけで考えることは容易ではない。だからこそ、一定のタイミングに来たら、医療や介護チームに終末期の状態や医療・ケアの選択肢についてしっかり聞いた上で、人生観や価値観に沿った意思決定をしたい。そのためには、本人、家族、医療者、介護者で話し合いを繰り返すことが大事だ。この話し合いを「人生会議」と呼び、厚生労働省も普及を促している。中村医師は言う。
「最期まで自分らしく生きぬくために、元気なうちから話し合いを始めておいたほうがよい。その話し合いで表明された意思は、基本的にケアに携わる全ての関係者に伝わるため、最期まで自分らしく、誇りを持って生きることにつながります」
 松岡かすみ
松岡かすみ



















